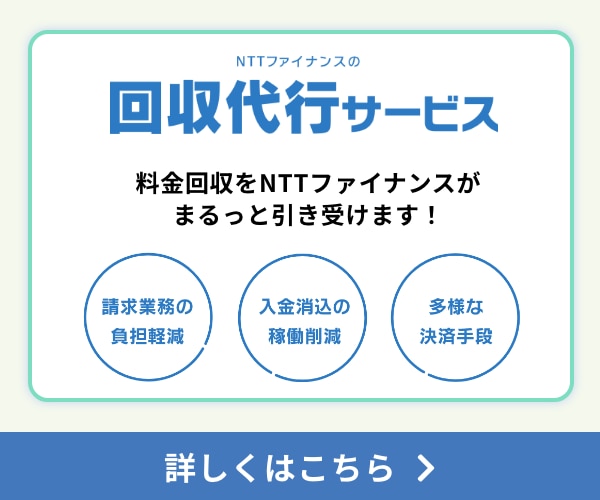事業計画とは?必ず含めるべき項目や成功するためのコツなどをわかりやすく解説
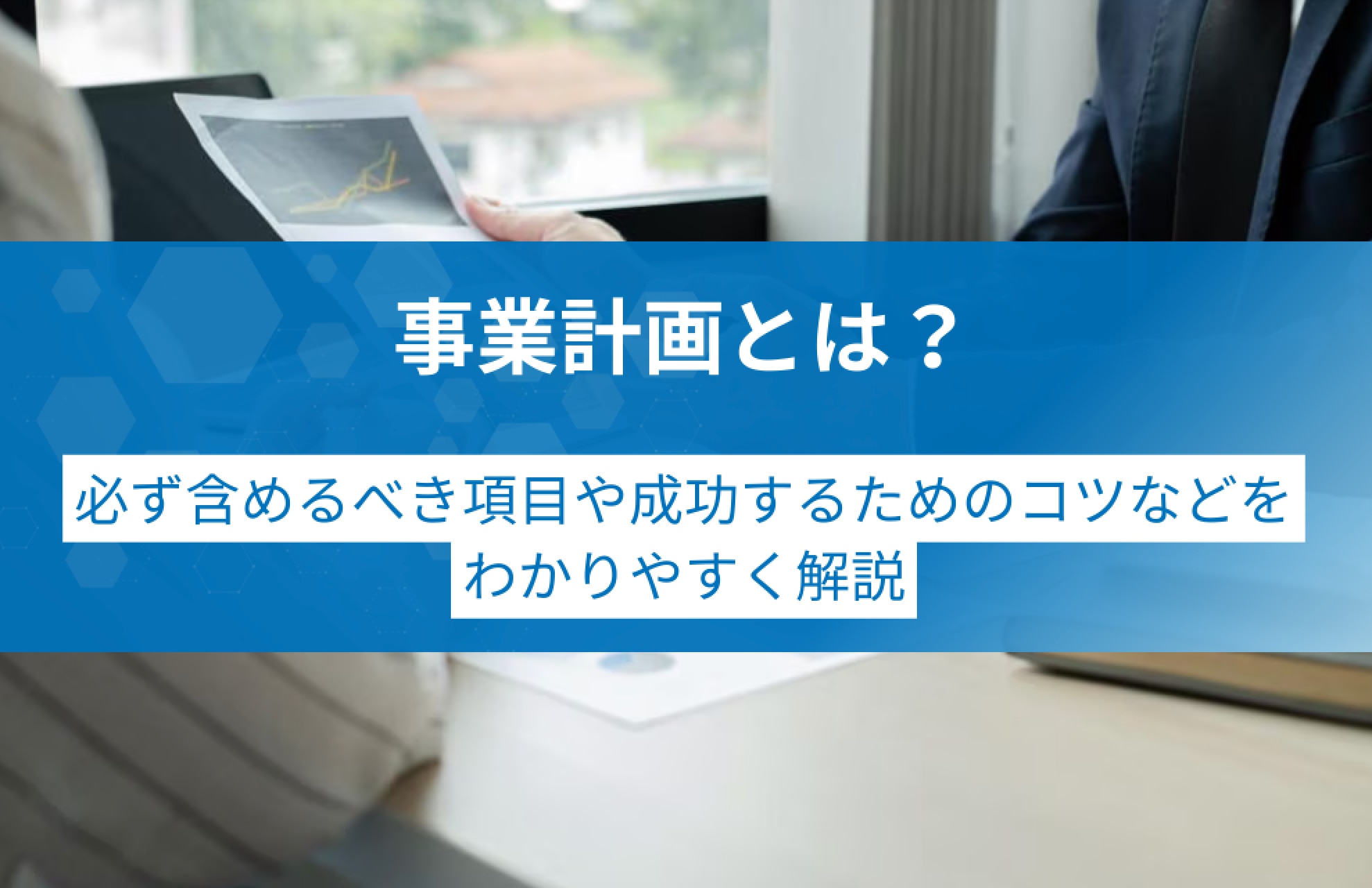
事業計画とは、会社や事業の目標達成に向けた具体的な道筋を示す「設計図」と同義です。経営の方向性を統一するために必須であり、事業を実施するうえで欠かせません。
とはいえ「どのように事業計画を考えればいいかわからない」とお悩みの方も多いでしょう。そこでこの記事では、下記の内容を紹介します。
- 事業計画における基本的な要素
- 事業計画の立て方
- 事業計画の失敗パターンと含めるべき項目
- 成功させるコツ
基礎からしっかりと解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次[非表示]
事業計画とは?基本的な4つの要素

事業計画とは、会社や事業の目標達成に向けた具体的な道筋を示す設計図です。ここでは、事業計画の基本的な要素について紹介します。
要素1.事業計画の定義と基本的な役割
事業計画とは「企業が将来の目標を達成するために立てる具体的な行動指針」のことです。計画には、下記の要素が含まれます。
|
事業計画の基本的な役割は、経営の方向性を明確にし全社員が同じ目標に向かって行動できるようにすることです。また、金融機関からの融資や投資家からの資金調達を行う際にも、事業の将来性を証明する重要な資料となります。
事業計画があることで日々の業務が目標達成にどう貢献しているかがわかりやすくなるので、効率的な経営には欠かせない存在です。
要素2.事業計画書との違いと使い分け
事業計画と事業計画書は密接に関連していますが、その役割には違いがあります。
事業計画 | 経営者の頭の中にある事業の方向性や戦略そのもの |
事業計画書 | その計画を文書として具体的に記載したもの |
事業計画書は、主に外部への説明や資金調達の場面で活用されます。例として、銀行融資の申請時や投資家へのプレゼンテーション時には、必ず事業計画書の提出が求められるでしょう。
内部での戦略検討や方針決定には事業計画を、外部との交渉や説明には事業計画書を使い分けることが重要です。
要素3.事業計画が必要になるタイミング
事業計画は「新しく事業を始めるとき」だけに必要なものではありません。代表的なタイミングとして、次のようなものが挙げられます。
【事業計画書が必要になるタイミングの例】
|
事業計画は単なる書類ではなく、経営を継続的に前進させるための道しるべです。適切なタイミングで作成・更新することが、企業の成長と安定につながります。
要素4.事業計画を作成するメリット
事業計画を作成する最大のメリットは「経営の方向性が明確になること」です。具体的な目標と達成方法が決まることで、限られた経営資源を効率的に配分できるようになります。
その他の主なメリットは、下記のとおりです。
【事業計画を作成する主なメリット】
|
金融機関や投資家は、しっかりとした事業計画がある企業に対してより積極的に資金提供を行う傾向があります。
事業計画の立て方における5つのステップ

効果的な事業計画を立てるには、下記のように体系的なアプローチが必要です。
【アプローチの5つの手順】
|
事業計画の立て方について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
事業計画を立てる際に避けるべき4つの失敗パターン

事業計画の作成では、多くの経営者が陥りがちな失敗パターンがあります。代表的な失敗例とその対策について、下記の4つを紹介します。
パターン1.専門用語ばかりで理解しにくい計画
事業計画書に専門用語や業界用語を多用すると、読み手が内容を理解できなくなってしまいます。特に、金融機関の担当者や投資家は必ずしもその業界の専門知識を持っているわけではないため、わかりやすい表現を心がけることが重要です。
専門用語を使う場合は必ず注釈や説明を加えて、誰が読んでも理解できるようにしましょう。
【読みやすくする例】
|
文章だけでなく、視覚的にわかりやすい図やグラフなども含めることで、より説得力のある事業計画書が作成可能です。
パターン2.作成することがゴールになった飾りのような計画
事業計画書を完成させることに満足してしまい、その後の実行や見直しを怠ってしまうケースがあります。
事業計画は作成することが目的ではなく「実際の経営に活用すること」が最も重要です。定期的な進捗確認と計画の更新を継続的に行いましょう。
【作成のポイント】
|
市場の変化に柔軟に対応できる経営体制を構築することで、事業の成功確率が大幅に向上します。
パターン3.リスク対策を考えない楽観的すぎる計画
すべてが順調に進むことを前提とした楽観的すぎる事業計画は、現実とのギャップが生じやすく危険です。市場環境の悪化や競合の参入、主要顧客の離脱など、さまざまなリスクを想定した対策を事前に検討しておきましょう。
リスク分析では、発生確率と影響度の両面から各リスクを評価し、優先順位を付けて対策を立案します。
【リスク分析の例】
|
前もって想定できるリスクを考えておくことで、危機的状況でも事業継続できる体制を整えられます。
パターン4.数値根拠が曖昧で現実性に欠ける内容
売上予測や市場規模の数値に明確な根拠がない事業計画は、信頼性に欠けてしまいます。
「なんとなく達成できそう」という感覚的な判断ではなく、市場調査データや類似事例の分析結果に基づいた客観的な根拠を示すことが必要です。
数値の算出過程を詳細に記載し、どのような前提条件で計算したかを明確にしましょう。
【算出過程の例】
|
国が出している情報をはじめとした「信頼できるデータソース」を複数参照し、多角的な視点から数値の妥当性を検証することが重要です。
事業計画の内容に必ず含めるべき4つの項目

効果的な事業計画を作成するには、下記4つの必要不可欠な項目を漏れなく盛り込むことが重要です。
順番に説明します。
項目1.事業コンセプトとターゲット顧客の明文化
事業コンセプトとは、その事業が社会にどのような価値を提供するかを表した核となる考え方です。単に商品を売るだけでなく、顧客の抱える問題をどう解決するか、どのような体験を提供するかを明確に言語化しましょう。
ターゲット顧客の設定では、年齢・性別・職業・収入レベルなどの基本属性に加えて、ライフスタイルや価値観も詳しく分析します。
【顧客の具体例】
|
事業コンセプトとターゲット顧客が明確になればマーケティング戦略や商品開発の方向性が決まり、一貫性のある事業運営が可能になります。
項目2.商品・サービスの詳細な説明
提供する商品やサービスの特徴、機能、品質基準を具体的に記載します。
競合他社の商品と比較して、どのような独自性や優位性があるかを明確にすることが重要です。価格設定の根拠や提供方法についても詳しく説明しましょう。
商品開発のプロセスや技術的な背景がある場合は、それらの情報も含めて記載します。特許や商標などの知的財産権を保有している場合は、競争優位性の根拠として必ず明記してください。
また、将来的な商品ラインナップの拡充計画や改良予定についても触れることで、事業の成長性をアピールできます。顧客にとってのメリットを具体的に示すことで、説得力のある内容になるでしょう。
項目3.売上計画と損益予測の数値化
売上計画では、月次および年次の売上目標を具体的な数値で設定します。
商品単価や販売数量、市場シェアなどの根拠を明確にして、実現可能性の高い予測を立てることが重要です。季節変動や市場トレンドも考慮に入れましょう。
【損益予測でやること】
|
【数値計画の作成でやること】
|
このような設定を実施しておけば、リスク管理の意識が高いことをアピールできます。
項目4.資金調達と運転資金の計画
事業開始から軌道に乗るまでに必要な資金の総額を算出し、調達方法を具体的に計画します。自己資金、銀行借入、投資家からの出資など、それぞれの調達手段のメリットとデメリットを検討して最適な組み合わせを決定しましょう。
運転資金の計画では、下記のサイクルを考慮して、月次の資金繰り表を作成しましょう。
|
特に事業開始直後は売上が少ない一方で費用は発生するため、十分な運転資金の確保が不可欠です。
資金計画の作成時は、予期せぬ支出や売上の遅れに備えて、ある程度の余裕を持った計画にすることがポイントです。資金不足は事業継続に直結する問題のため、慎重な検討が求められます。
事業計画を成功させる3つのコツ

事業計画を確実に成功に導くには、計画段階での適切な準備と実行段階での継続的な改善が欠かせません。事業計画を成功させる3つのコツを順番に解説します。
コツ1.現実的で達成可能な数値目標を設定する
事業計画の成功には、背伸びしすぎない現実的な数値目標の設定が重要です。市場調査データや競合他社の実績を参考にして、客観的な根拠に基づいた目標値を算出しましょう。
過度に楽観的な目標は、実行段階で大きな修正が必要になり、関係者の信頼を失う原因となります。
目標設定の際は、短期・中期・長期の時間軸を明確に分けて考えることが効果的です。
【目標の例】
|
また、最良・標準・最悪の3つのシナリオを用意すると、柔軟性のある計画にすることが可能です。現実的な目標設定により、着実な成長を実現できる可能性が高まります。
コツ2.リスク対策を具体的に計画に組み込む
事業運営には必ずリスクがともなうため、想定されるリスクとその対策を事前に計画に盛り込むことが成功の鍵となります。
【想定されるリスク】
|
各リスクに対しては、発生確率と影響度を評価して優先順位を付けて対策を立案します。例えば、主要取引先への依存度が高い場合は、新規顧客の開拓を強化して売上の分散化を図る具体的な計画を策定するなどです。
リスク対策の実効性を高めるには、定期的な見直しと更新が必要です。
コツ3.定期的な進捗確認と第三者意見の活用
事業計画の成功には、計画の実行状況を定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を行う仕組みが不可欠です。月次での売上実績、顧客獲得数、コスト推移などの重要指標をモニタリングし、計画との差異を早期に発見できる体制を整えましょう。
進捗確認では、数値面だけでなく、市場環境の変化や競合の動向についても併せて分析することが重要です。外部環境の変化が事業に与える影響を適切に評価し、必要に応じて戦略の見直しを行います。
第三者の客観的な意見を積極的に取り入れることも成功の重要な要素です。業界の専門家、経営コンサルタント、既存顧客などから定期的にフィードバックを得ることで、自社では気付かない課題や改善点を発見できます。
事業を円滑に進めるなら「法人"ビリングONE"」もおすすめ
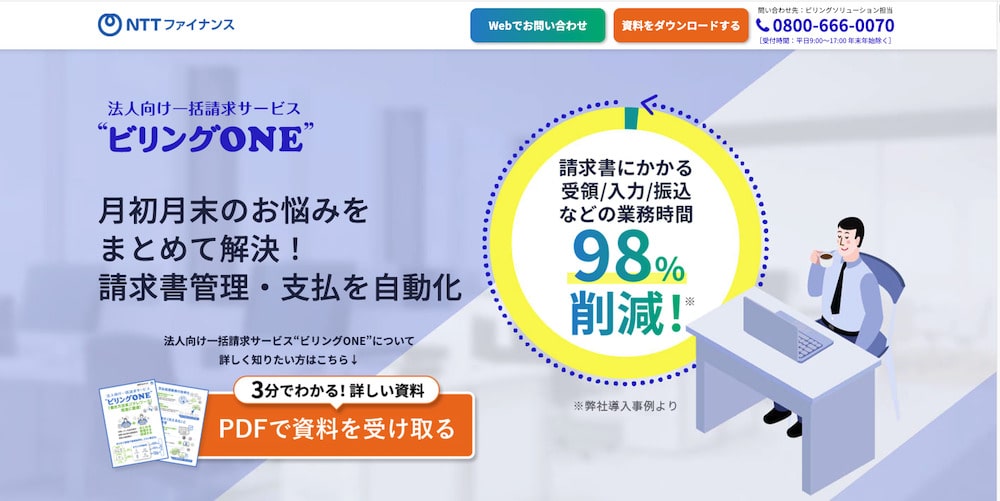
事業計画を立てたのち、実際に事業を始めると請求書まわりで苦労するケースが少なくありません。
具体的には「請求書業務を効率化したい」「支払期限が異なる請求書の処理が大変。大量に届く請求書を1枚にまとめたい」などがあります。
そのような方には、NTTファイナンスの「法人"ビリングONE"」がおすすめです。
「法人"ビリングONE"」は、支払期限が異なる請求書をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 要問い合わせ |
対象の請求書 | 通信料金・公共料金・その他 |
複数の拠点ごとにバラバラ届く請求書や、支払期限が異なる請求書を1枚の電子請求書(紙請求も可)にまとめることで、支払い処理を1回にできます。
従来の支払い作業・開封・保管の負担を軽減できるため、複数枚届く請求書や何通も届くメールの処理にかかっていた経理業務の大幅な効率化が可能です。
インボイス制度にも対応している「法人"ビリングONE"」の詳細は、下記からサービス資料をダウンロードのうえご確認ください。
\請求書の受領〜管理・支払いまで完全自動化!/
事業計画はしっかりとプランを立てて練ろう

【本記事のまとめ】
|
事業計画は、内容ももちろん大事ですが「作ること」が目的になってしまわないことも非常に重要です。作った事業計画をどのように活用していくかを常に考えて、事業を発展させるために活かしていきましょう。
実際に事業を始めたあとに、切っても切り離せないのが料金回収です。サービスを提供する以上は金銭のやり取りが必ず発生し、この手間を減らしたいと考える人も少なくありません。そこで金銭のやり取りの負担を軽減するなら、NTTファイナンスの「回収代行サービス」がおすすめです。
「回収代行サービス」は請求情報を作成するだけで、NTTファイナンスが事業者様にかわって顧客(エンドユーザー)へ請求を行うサービスです。収納状況は管理画面上で確認できるため、入金状況を確認する手間が省けます。
また、支払い方法は電話料金合算(※)・口座振替・払込票(請求書送付)・クレジットカードなど30以上から選択でき、利便性の高い決済手段のご提供が可能です。
※電話料金合算:NTTグループの通信料金と一緒にご請求するお支払い方法です。
「電話料金合算」で高い回収率を実現する本サービスの詳細は、下記のバナーより無料で資料をダウンロードしてご覧ください。
\料金回収にかかっている時間を大幅に削減!/

 ▲すぐにダウンロードできます!
▲すぐにダウンロードできます!