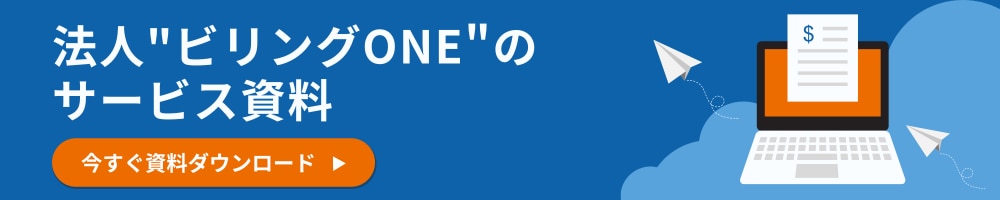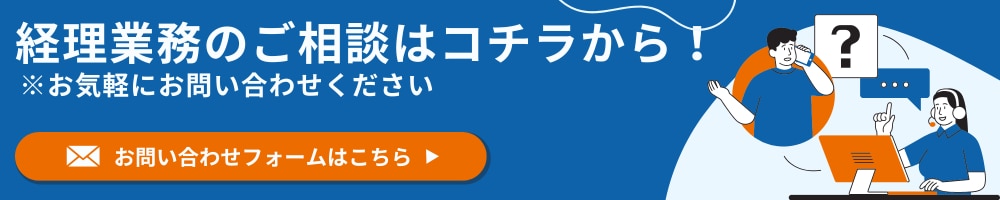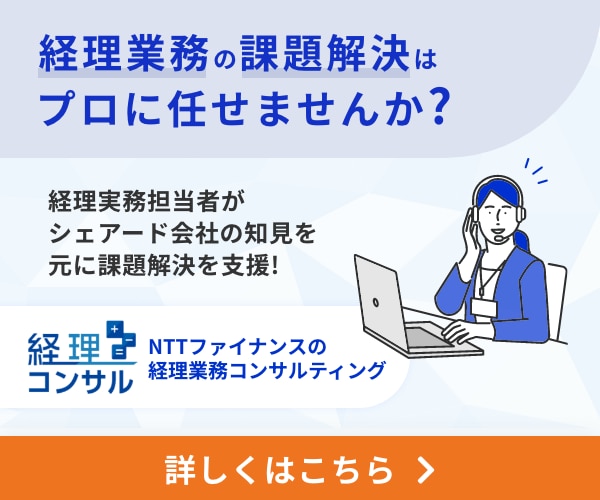炭素会計とは?5つのメリットや計算方法など知りたいこと完全ガイド
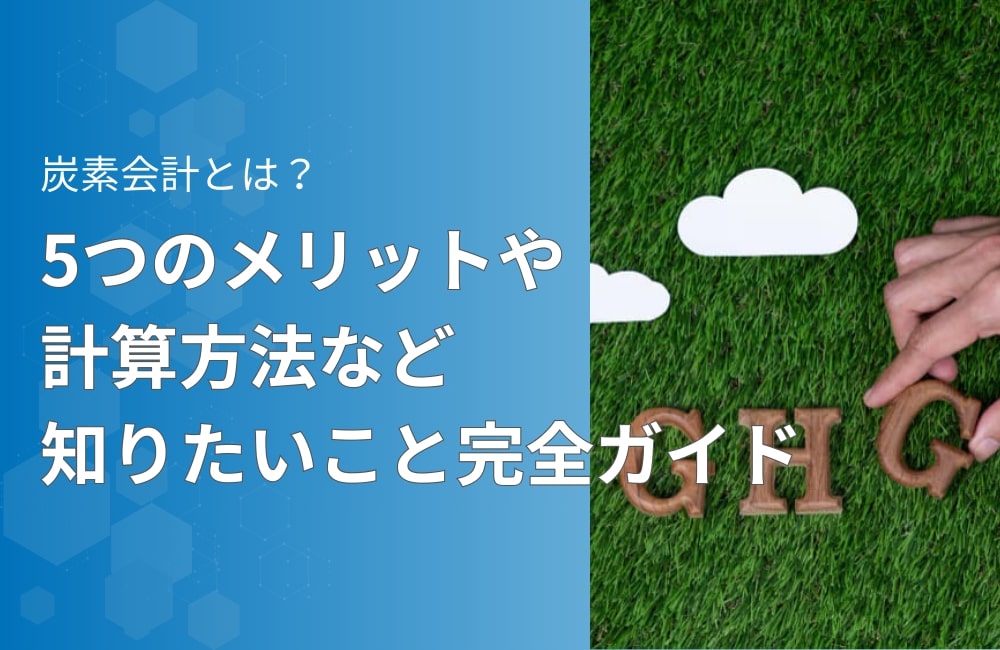
炭素会計とは、企業や組織が事業活動を通じて排出する温室効果ガス(GHG)の排出量を算定・管理・報告するための体系的なプロセスのことです。
企業や組織が自身の活動による二酸化炭素やその他の温室効果ガスの排出量を正確に把握することが可能になり、その先のさまざまなメリットを享受できます。
そこでこの記事では、下記の内容をまとめました。
- 炭素会計の基礎
- 炭素会計導入で得られるメリット
- 炭素会計で把握する3つのスコープとGHG排出量
- 炭素会計実践における重要ポイント
炭素会計の基礎から重要ポイントまで網羅して紹介しますので、ぜひ読み進めてみてください。
目次[非表示]
炭素会計とは?

炭素会計とは、企業や組織が事業活動を通じて排出する温室効果ガス(GHG)、特に二酸化炭素(CO2)の排出量を算定・管理・報告するための体系的なプロセスです。
カーボンニュートラル(※)実現に向けた第一歩となり、環境戦略の基盤となる重要な取り組みのことを指します。
(※)カーボンニュートラルとは |
財務会計との関係性
炭素会計は財務会計とパラレル(並列)な関係にあるといわれています。
財務会計 | 企業の経済活動を「お金」の面から可視化 |
炭素会計 | 「CO2排出量」という観点から事業活動を評価 |
経営の柱として相互補完的な役割を果たしている関係性です。
財務会計は日々の取引を記録し、決算書を作成して投資家や株主に開示するものです。炭素会計においても、排出量の算定から情報開示までの一連のプロセスが確立されています。
財務部門が重要な役割を担うのは、炭素会計でも同様です。GHG排出量の算定には請求書や帳簿といった記録の確認が必要であり、情報開示の際には財務情報と組み合わせて報告することが求められるため、財務活動と一体的に進める必要があります。
炭素会計の計算方法
炭素会計における排出量の基本的な算定式は、下記のとおりです。
排出量=活動量×排出原単位 |
活動量は事業活動の規模を示す量(電力使用量や燃料消費量など)を指し、排出原単位はその活動によって発生するCO2排出量の係数を意味します。
項目 | 説明 |
活動量 | 事業活動の規模を示す数値(例:電力使用量、燃料消費量) |
排出原単位 | 活動ごとに発生するCO2排出量の係数(例:燃料1kLあたりの排出量) |
例えば、ガソリンの排出原単位は「2.32 t-CO2/kL」で、1キロリットルの消費で2.32トンのCO2が排出されることになります。100キロリットル使用した場合のCO2が排出される計算は下記のとおりです。
100kL×2.32 t-CO2/kL=232トン(232トンのCO2が排出されることになる) |
CO2以外の温室効果ガスについては、それぞれの温暖化係数(GWP)を乗じて「CO2換算(CO2eq)」で表示します。メタン(CH4)はCO2の25倍、六フッ化硫黄(SF6)は22,800倍の温室効果があるため、それぞれの排出量に温暖化係数をかけて算出します。
ガスの種類 | 温暖化係数(GWP) | 計算例 |
メタン(CH4) | 25 | 1tのCH4 = 25t-CO2eq |
六フッ化硫黄(SF6) | 22,800 | 1tのSF6 = 22,800t-CO2eq |
実務では、環境省が定めた排出係数や産業連関表 、IDEA(国内の製品・サービスの環境負荷情報データベース)などを活用して計算を行います。
また、企業の炭素会計では自社の活動だけでなく、原材料の調達や物流など、サプライチェーン全体の排出量も考慮する必要があります。
算定精度を高めるために、サプライヤー(供給業者)が独自に計測・記録した一次データの取得も重要です。
炭素会計導入で得られる5つのメリット

炭素会計の導入は、単に環境対応としてだけではなく、企業にとって多面的な価値をもたらします。適切に実施することで得られるメリットは下記の5つです。
順番に解説していきます。
メリット1.環境負荷の可視化と削減対策の具体化
炭素会計を導入することで、企業や組織が自身の活動による二酸化炭素やその他の温室効果ガスの排出量を正確に把握可能です。
これにより、下記のような取り組みにつなげることができます。
|
例えば、エネルギー消費が特に多い工程や設備を特定し、そこに焦点を当てた改善策の実施は、CO2排出量の削減に効果的です。
この「可視化のプロセス」により従業員の環境意識も高まり、全社的な取り組みを促進する効果も期待できます。
メリット2.コスト削減と経済性の向上
炭素会計の導入は環境対策であると同時に、経済的なメリットをもたらします。
排出量の可視化を通じてエネルギーや資源の無駄な使用を特定し「省エネルギー対策」を実施することで、下記のように直接的なコスト削減につながるケースが少なくありません。
|
さらに、将来的な炭素税や排出量取引制度の導入に備えることで、将来の財務リスクの低減も可能です。
規制強化が予想されるなかで早期に対応することで、急激なコスト増加を避けて競争優位性を確保できる可能性が高まります。
メリット3.投資家・金融機関からの評価向上
ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視した投資)を重視する投資家にとって、企業の環境対策は投資判断の一つの要素です。
炭素会計を実施してその情報を適切に開示することで、環境を重視する投資家や金融機関からの高い評価が期待できます。
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やCDPなどの国際的な枠組みに準拠した情報開示は、ESGを意識する投資家に対して企業の気候変動リスク管理能力をアピールするのに効果的です。
金融機関の中には融資先の気候変動リスクに敏感になっている企業もあり、適切な炭素会計を実施することが有利な資金調達につながる場合があります。
メリット4.ブランド価値と社会的信頼の構築
炭素会計を導入して積極的に環境対策に取り組む企業は、環境意識の高い消費者や取引先から支持される可能性が高まる点もメリットの一つです。
環境への配慮が企業選択の重要な基準となりつつある現代において、炭素会計に基づく具体的な取り組みはブランド価値の向上にかかせない存在になり得ます。
また、取引先企業もサプライチェーン全体での排出量削減を求められるなか、炭素会計を実施していることが取引条件となるケースも少なくありません。
自社で具体的な取り組みを行うことで、ビジネスパートナーからの信頼を獲得し、長期の関係構築が可能です。
メリット5.新たなビジネス機会の創出
新たなビジネスチャンスの発見にもつながるのが、炭素会計のメリットです。排出量データの分析を通じて製品やサービスの環境負荷を把握すれば、下記のような効果が期待できます。
|
自社の炭素排出削減ノウハウや技術は、同業他社やサプライチェーン上の企業に提供できる「価値ある資産」です。
知見の共有を通じて、コンサルティングや技術提供などの新規事業展開の可能性も広がります。
炭素会計で把握する3つのスコープとGHG排出量

温室効果ガス排出量の算定において重要な指標となるのが「スコープ1・2・3」です。「GHGプロトコル」に基づく国際的な基準で排出源を3つに分類することで、企業活動に関連するあらゆる排出量を包括的に把握できます。
項目 | 内容 |
スコープ1 |
|
スコープ2 |
|
スコープ3 |
|
これら3つのスコープを網羅することで、事業活動全体の環境影響を正確に評価し、効果的な削減戦略を立案することが可能です。
グローバル企業では、サプライチェーン全体の排出量把握がすでに当たり前に取り組まれています。
炭素会計実践における3つの重要ポイント

炭素会計を効果的に実践するためには、単に排出量を計測するだけでなく、具体的な戦略と実行が不可欠です。
ここでは、炭素会計を成功させるための3つの重要なポイントについて解説します。
ポイント1.「省エネ」「電化」「再エネ」の戦略的活用
炭素会計で把握した排出量を効果的に削減するには、「省エネ」「電化」「再エネ」の3つの施策を戦略的に組み合わせることが重要です。
順番にみていきましょう。
施策1.省エネ
まず「省エネ」は、最も基本的かつ即効性のある施策です。
【省エネの具体例】
|
エネルギー使用量そのものを削減することで直接的なCO2排出削減につながります。省エネは初期投資が比較的小さく、投資回収も早いことから、最初に取り組むべき対策です。
施策2.電化
「電化」は、化石燃料を使用する設備や機器を電気式に転換することです。
【電化の具体例】
|
これらを実施すれば、直接的な排出を削減できます。電化はカーボンニュートラル実現の鍵となる重要なステップです。
施策3.再エネ
「再エネ」は、電力の調達先を太陽光や風力などの「クリーンエネルギー」に切り替えることです。
自社での再エネ発電設備の導入や再エネ電力の購入契約(PPA)、グリーン電力証書の活用などを通じて、電力由来の排出量を大幅に削減できます。
紹介した3つの施策を組み合わせることで、効率的かつ効果的な排出削減が可能です。
ポイント2.社内炭素価格の設定とグリーン調達の推進
企業の脱炭素化を推進するための具体的な取り組みとして、「社内炭素価格の設定」と「グリーン調達の推進」が有用です。
社内炭素価格の設定 |
|
グリーン調達の推進 |
|
設備投資を検討する際に社内炭素価格を加味した場合、もし初期コストが高かったとしても、CO2排出量の少ない選択肢が長期的には経済的に有利となるケースがあります。
またグリーン調達は、サプライヤーに対してCO2排出量データの提供を求め、低炭素製品を優先的に調達することで、スコープ3の排出量削減に貢献します。
ポイント3.適切な情報開示とステークホルダーコミュニケーション
炭素会計の最終段階として重要なのが、適切な情報開示とステークホルダーとのコミュニケーションです。
排出量データをそのまま公表するだけでは信頼性を高められません。信頼性と透明性を高めるためには、下記のような項目を体系的に開示することが有用です。
|
情報開示においては、CDPなどの国際的に認知されたフレームワークに準拠することが望ましいです。これらのフレームワークは、気候変動関連の情報を財務情報と関連付けて開示することを求めており、投資家にとって有用な情報となります。
また、顧客や取引先、地域社会などさまざまなステークホルダーとのコミュニケーションも下記のように積極的に行うべきです。
|
多様なチャネルを通じて自社の取り組みを発信してみましょう。
GHG排出量を可視化できるツールとの連携なら「法人"ビリングONE"」がおすすめ

GHG排出量を可視化できるツールと連携し、経理業務を効率化するならNTTファイナンスの「法人"ビリングONE"」がおすすめです。
「法人"ビリングONE"」は、支払い期日が異なる通信費や公共料金などの請求書をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
炭素会計に重要な「GHGの可視化」ができるツールとの連携も可能で、可視化できるツール側で課題になりがちな「データ投入における手間の削減」に貢献できます。
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 要問い合わせ |
複数の拠点ごとにバラバラ届く請求書や、支払い期日が異なる請求書を1枚の電子請求書(紙請求も可)にまとめることで、支払い処理を1回にできます。
従来の支払い作業・開封・保管の負担を軽減できるため、複数枚届く請求書にかかっていた経理業務の大幅な効率化が可能です。
さらに、会計処理に合った勘定科目の自動設定が備わっている他、任意の仕訳項目の設定も行えます。
インボイス制度にも対応している「法人"ビリングONE"」の詳細は、下記からサービス資料をダウンロードのうえご確認ください。
\ クラウド上で管理が可能! /
▲初期導入コスト無料!
今後活発化する「炭素会計」を積極的に導入しよう

【本記事のまとめ】
|
炭素会計は、環境負荷を可視化する取り組みを通じて、環境への配慮を促進します。同時に、ブランドの価値向上やステークホルダーからの信頼獲得など、企業にとってさまざまなメリットをもたらします。
一方で、具体的な戦略立案&実行や適切な情報開示など、単純に炭素会計にするだけでは最大限の効果を得られません。
この記事を参考に、重要ポイントを押さえたうえで積極的に炭素会計を導入してみてください。
なお、炭素会計の取り組みにあたり、「そもそも自社の経理の状況を改善したい」と考えている方にはNTTファイナンスの「経理業務コンサルティングサービス」がおすすめです。
「経理業務コンサルティングサービス」は、NTTグループ900社を超える経理を支えるプロフェッショナルが在籍しています。
経理部門における業務可視化支援やDX支援も可能で、社員の業務理解向上や効率化など、経理業務そのものの課題解決を促進することが可能です。
サポート内容が気になる方は、下記のバナーをクリックのうえお気軽にご相談ください。
\NTTグループ900社超えの経理のプロフェッショナルがサポート!/