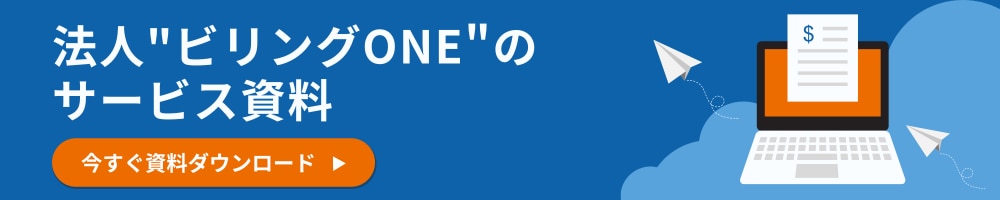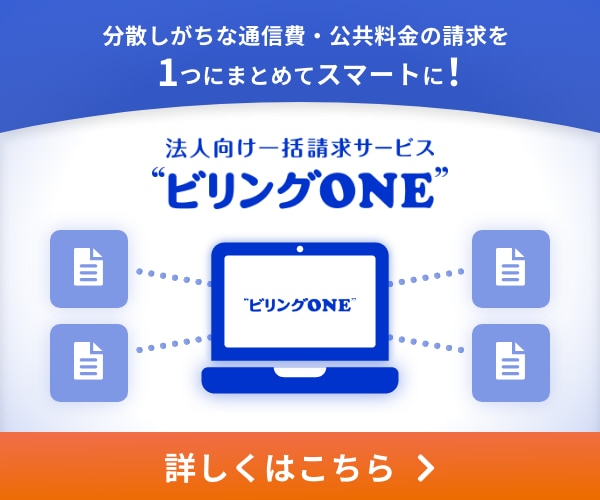自動仕訳とは?メリットや方法、効率化におすすめのサービスも紹介
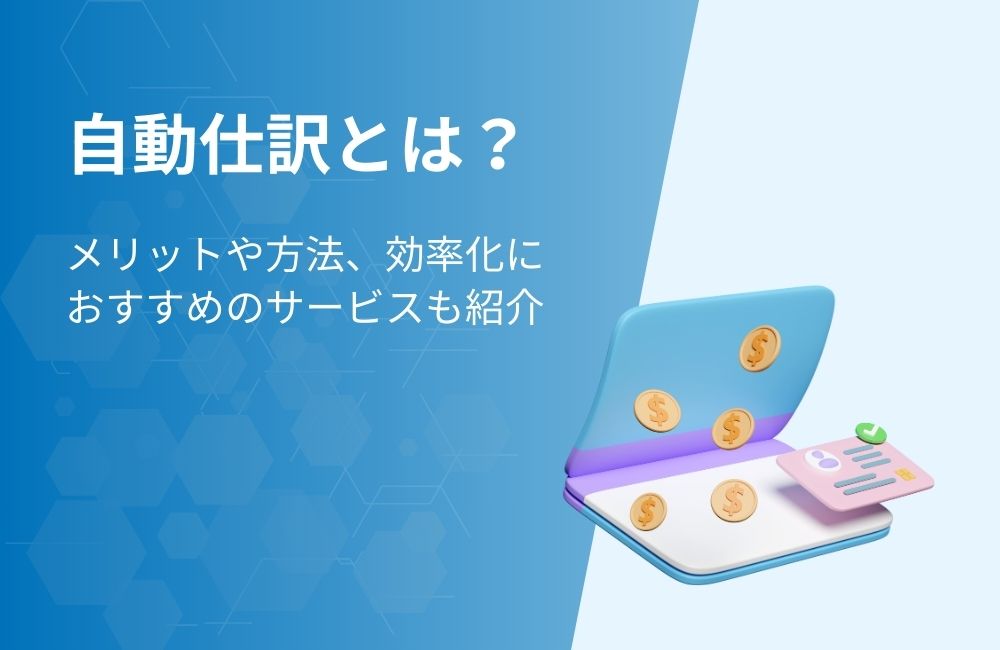
手作業による日々の仕訳業務は負担が大きく、起こりうる仕訳ミスも担当者の悩みの一つです。
そこで本記事では、仕訳の自動化に関心のある経理部門の方に向けて、仕訳自動化のメリットや具体的な方法、導入時のポイントなどを解説します。
なおNTTファイナンスでは、自社の会計処理にあった勘定科目を自由に設定し、仕訳の自動化が可能なサービス「法人“ビリングONE”」を提供しています。
支払い期日が異なる請求書(対象:通信費・公共料金・その他)をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求できる「法人“ビリングONE”」の詳細は、下記のバナーをクリックのうえ、資料をダウンロードしてご覧ください。
\ 仕訳の設定内容はいつでも変更OK! /
▲初期導入コスト無料で利用可能
目次[非表示]
自動仕訳とは?

自動仕訳とは、あらかじめ設定されたルールに基づいて、取引データを自動的に「借方」と「貸方」で適切な勘定科目に分類し記録することです。
例えば、下記のようなことができます。
|
またAIを使用した自動仕訳では、次のような流れでAIが仕訳ルールを学習していきます。
|
AIに学習させるには、経理担当者の確認・修正作業も必要になります。
仕訳は税金の計算や決算書にも影響するため、経営者がお金の流れや財務状況を正確に把握し、会社運営上のさまざまな判断や決定にかかわる重要な業務です。
なお、経理部門に配属されたばかリという方には、勘定科目の分類や基本ルールなどを解説している下記の記事がおすすめです。併せて参考にしてください。
自動仕訳の主な3つの仕組み

本章では、自動仕訳の仕組みを大きく3つに分けて解説します。
自動仕訳では、取引内容のキーワードを認識したり、銀行口座やクレジットカードの明細データを直接取り込んだりと、いくつかの仕組みがあります。 仕訳の自動化をイメージしやすくするために、それぞれの仕組みをみていきましょう。
仕組み1.設定したルールによる自動仕訳
1つ目は、設定したルールベースと呼ばれる仕組みの自動仕訳です。あらかじめ設定した条件にしたがって、自動で仕訳を行います。
例えば、「取引先名が〇〇電力なら水道光熱費」「金額が毎月同額なら地代家賃」といったように、パターン化された条件をもとに自動処理を行うやり方です。毎月同じような取引が多い場合や、取引のパターンがある程度決まっている場合に有効です。
設定するルールの例は、下記を参考にご覧ください。
ルールを設定する項目 | 項目の詳細 | 自動仕訳先の勘定科目や計上する内容 |
摘要欄と取引内容 | 電話代、通信費 | 通信費 |
文房具、コピー用紙 | 消耗品費 | |
取引先 | 〇〇電力、〇〇ガス | 水道光熱費 |
〇〇不動産 | 地代家賃 | |
金額 | 定額の金額(家賃など) | 地代家賃 |
10万円以上の備品購入 | 固定資産 | |
日付・周期 | 毎月25日の同じ金額 | 給与 |
四半期ごとの同額 | 保険料 | |
入出金の流れ | 得意先からの銀行振込での入金 | 売掛金の回収 |
カード決済 | 未払金 |
一度ルールをきちんと設定してしまえば、そのルールに合致する取引はスピーディーに処理されます。
ただし、新しい取引先や今までにないパターンの取引が発生した場合、その都度新しいルールを追加したり、既存のルールを見直したりする手間が発生することも押さえておきましょう。
仕組み2.AIを活用した自動仕訳
2つ目は、AIを活用した自動仕訳です。
過去に入力された膨大な仕訳データや取引のパターンをAIが学習することで、新しい取り込みデータの勘定科目を推測し、仕訳を提案・生成する仕組みになっています。
ルールベースでは対応しきれない、文脈や言い回しの違いを含んだ取引内容にも、柔軟に対応できる点が特徴です。
AIによる判断の例は下記のとおりです。
AIの機能 | 詳細 | 自動仕訳先の勘定科目や計上する内容 |
言語処理による推測 | 新宿駅からタクシーで顧客訪問 | 旅費交通費 |
プロジェクト完了の打ち上げ | 福利厚生費 | |
画像認識による領収書解析 | レシート画像から店舗名(〇〇文具)と商品名を認識 | 消耗品費 |
手書き文字(得意先名と手土産)の解読 | 交際費 | |
異常検知と提案 | 同じ日に複数の交通費がある | 出張旅費として一括処理を提案 |
月末に集中している特定の取引先 | 定期取引として自動化ルール作成を提案 |
使えば使うほどAIの学習が進み仕訳の精度も上がっていきますが、AIの判断が100%正しいとは限りません。AIが提案した仕訳を、人間が最終確認する作業は必要です。
AIの活用により、単純なルールでは対応できないものや高度な仕訳の自動化にも期待が高まっています。
仕組み3.OCR連携による自動仕訳
3つ目は、OCR(光学的文字認識)連携による自動仕訳です。
OCRとは、紙の請求書や領収書に印刷された文字を、スキャナーやスマートフォンのカメラで読み取り、テキストデータに変換する技術をいいます。
OCR連携による自動仕訳は、データ化された情報をもとに自動で仕訳を作成する仕組みです。活用例は、下記を参考にしてください。
OCR連携の例 | 詳細 | 自動仕訳先の勘定科目や計上する内容 |
レシートや領収書の読み取り | ○○タクシー、乗車区間:新宿→渋谷、1,200円 | 旅費交通費 |
〇〇石油、レギュラー 30L、4,500円 | 車両費 | |
請求書の読み取り | NTT、基本料金+通話料、8,900円 | 通信費 |
株式会社〇〇、システム開発費、200,000円 | 外注費・未払金 | |
手書き伝票・帳票の処理 | 5/20、交通費、新幹線代、15,000円、出張:大阪 | 旅費交通費 |
商品A×10個、単価500円、合計5,000円 | 仕入・未払金 |
OCR連携により、紙ベースの業務からデジタル会計への移行が大幅に効率化され、入力ミスの削減と処理速度の向上が期待できます。
ただし、デザイン性の高い複雑なレイアウトの書類、印字がかすれていたり汚れていたりする書類などは正確に読み取れない場合があるため、留意が必要です。
また、スキャンするときの画像の解像度も精度に影響することを理解しておきましょう。
自動仕訳を導入する5つのメリット

本章では、仕訳を自動化することで得られる代表的な5つのメリットについて解説します。
これらのメリットを理解することで、自動仕訳導入の価値がより明確になります。
メリット1.経理業務の大幅な時間短縮
自動仕訳を導入する最大のメリットは、何といっても仕訳業務にかかる時間を大幅に短縮できることです。
月次仕訳処理の件数は、企業によっては数百から数千件に及ぶことがあります。
膨大な書類を1枚1枚確認し、会計ソフトに手入力していた作業の多くを自動化できれば、仕訳業務に費やしていた時間の劇的な削減が可能です。
なお下記の記事では、日々の経理業務で発生するおそれのある訂正仕訳について詳しく解説しています。具体的な訂正仕訳の方法を知りたい方は、併せてご覧ください。
メリット2.ヒューマンエラーの削減
仕訳を自動化するシステムは、設定されたルールや学習データに基づき一貫した処理を行うため、勘定科目の選択ミスや単純な入力ミスは起こりにくくなります。
人間の手作業では、どんなに気をつけていても入力ミスや勘定科目の選択ミスといったヒューマンエラーを完全にゼロにすることは難しいものです。金額の桁を間違えるなどのミスは、後々大きな手戻り作業や、場合によっては誤った経営判断につながるリスクも否定できません。
一方で、銀行明細やクレジットカードの利用履歴を直接取り込む機能を使えば、金額の転記ミスもなくなり、結果として会計データの正確性と信頼性が大きく向上します。
なお、NTTファイナンスの「法人“ビリングONE”」の自動仕訳機能により、手作業によるミスが軽減した企業様の例を下記記事でご紹介しています。
ぜひ併せてご覧ください。
メリット3.属人化の防止と業務の標準化
仕訳の自動化では、仕訳ルールや処理の手順がシステム上などに明文化・可視化されるため、担当者ごとの判断のブレがなくなります。誰が作業しても一定の品質を保つ業務の標準化にも効果的です。
経理業務は専門性を求められることが多く、複雑な仕訳ルールや長年の勘に頼った処理が属人化しやすい傾向にあります。担当者が急に休むと業務が滞ったり、退職時の引継ぎで苦労したりする経理部門の環境改善も期待できます。
メリット4.ペーパーレス化の推進
自動仕訳ができるシステムを取り入れることで、帳票や伝票のやり取りが紙ベースからデジタルへ移行し、経理業務のペーパーレス化が一気に進みます。
電子化により、印刷費・郵送費・保管場所など、紙にまつわるさまざまなコストの削減にもつながります。
また、ファイリングや仕分けといった作業に費やしていた時間も削減され、経理担当者はより付加価値の高い業務(例:データ分析やレポート作成)に集中できるようになる点もメリットの一つです。
ちなみにNTTファイナンスでは、毎月バラバラに届く通信費や光熱費などの紙の請求書の保管が不要になる「法人“ビリングONE”」のサービスを提供しています。
支払い期日が異なる請求書(対象:通信費・公共料金・その他)をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
複数の拠点のものや支払い期日が異なる請求書を1枚の電子請求書(紙請求も可)にまとめることで、支払い処理を1回にできるため、ペーパーレス化推進にも役立ちます。
自動仕訳機能を搭載しており、勘定科目が自動で選択されるのはもちろん、カスタマイズ可能な仕訳ルールの設定にも対応しているのが特長です。
クラウド上で管理可能な「法人“ビリングONE”」の詳細は、下記バナーをクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。
\ 会計システムとの連携も可能! /
▲1分でダウンロード完了!
メリット5.経営状況のリアルタイムでの可視化
仕訳処理に時間がかかり、月次決算の数字が出てくるのが数週間後という状況では、変化の速いビジネス環境において、迅速な意思決定は望めません。
一方で、自動仕訳システムを導入すれば、日々の取引データが効率的かつ正確に処理されます。その結果、手作業によるデータの収集・入力・集計・チェックといった従来のプロセスが短縮され、月次決算の大幅な早期化が図れる点もメリットです。
売上状況や部門別の収益など、財政状態をタイムリーに把握でき、的確な経営判断につながります。
自動仕訳の4つの注意点

自動仕訳においては、下記のような点に注意が必要です。
注意点 | 具体的な内容 |
すべての取引が自動化できるわけではない |
|
人の手による確認が不可欠 |
|
定期的な見直しとメンテナンスが必要 |
|
システム依存によるリスク管理も必要 |
|
導入時は、会計の専門家やシステム担当と連携し、慎重に設計を行いましょう。
仕訳を自動化する4つの方法

本章では、「どこからデータを取得するか」という視点で、仕訳を自動化する方法を大きく4つに分けて、それぞれの特徴を紹介します。仕訳を自動化する際の参考にしてください。
方法 | メリット | デメリット | |
1 |
|
| |
2 |
|
| |
3 |
|
| |
4 |
|
|
方法1.手入力データをExcelで自動仕訳する
表計算ソフトのExcelに取引内容や金額を手入力し、関数やマクロで取引先名や摘要欄のキーワードから適切な勘定科目を自動で振り分ける方法です。
この方法は下記のような企業に向いています。
|
関数に詳しくなくともAIなどで関数を調べて入力しルールを設定できるなど、手軽に始められるのがメリットです。
一方で、クレジットカードの利用履歴を自動で取り込む機能などは基本的になく、本格的な自動仕訳システムに比べると、機能面やセキュリティ面での課題が多い点に留意しましょう。
方法2.銀行口座連携などで自動仕訳する
多くの会計ソフトが搭載している機能で、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取得し、AIが勘定科目を推測して仕訳を作成する方法です。
データ取得から仕訳作成まで一連の流れを自動化できるため、恩恵が大きいのがメリットで、下記のような企業に向いています。
|
現金取引では手入力が必要になるなど、自動仕訳が適用されないケースがあることも理解しておきましょう。
方法3.紙書類を読み取り自動仕訳する
紙の領収書や請求書をスマートフォン撮影やスキャンなどで読み取り、仕訳を自動化する方法です。
スマートフォンのカメラで領収書を撮影するだけで、OCR(光学的文字認識)技術などにより日付、金額、取引先名などを自動で読み取り、仕訳を作成します。
この方法は下記のような企業に向いています。
|
経費精算の承認フローも自動化できるメリットがある一方で、乱雑に書かれた文字や汚れた書類などは読み取りが困難な点に留意しましょう。
方法4.ほかのシステムと連携し自動仕訳する
販売管理や給与計算など、ほかの業務システムからデータを取得し、自動で仕訳する方法です。システム間連携から仕訳作成までの一連の工程を自動化できる点が大きなメリットです。
この方法は下記のような企業に向いています。
|
既存の業務システムと会計ソフトを連携させることで、売上計上、仕入計上、給与計算などの取引を自動仕訳に反映できます。
その一方で、システム連携の初期設定が複雑なことやシステム障害時の影響が大きいことなどには留意しましょう。
自動仕訳を導入する際に押さえておきたい5つのポイント

最後に、仕訳の自動化を導入する際に押さえておきたい5つのポイントを一覧で紹介します。
ポイント | 具体的な内容 |
1.導入・運用コストの確認 |
|
2.既存システムとの連携性 |
|
3.セキュリティ対策とサポート体制 |
|
4.自動化したい業務範囲の明確化 |
|
5.従業員への周知と教育 |
|
ポイントを事前に確認し、自社の業務や体制に合った準備を進めることで、仕訳の自動化をより効果的に活用できます。
仕訳業務を自動化して業務効率化を実現しよう

【本記事のまとめ】
|
自動仕訳による請求業務の負担軽減なら、NTTファイナンスが提供する「法人“ビリングONE”」がおすすめです。
「法人"ビリングONE"」は、支払い期日が異なる請求書(対象:通信費・公共料金・その他)をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
自動仕訳機能が搭載されており、仕訳作業を効率化できるだけでなく、勘定科目も柔軟に設定できるため、経理担当者の業務負担を軽減します。
インボイス制度にも対応している「法人"ビリングONE"」の詳細は、下記のバナーからサービス資料をダウンロードのうえご確認ください。
\ 仕訳以外の請求業務も効率化! /
▲初期導入コスト無料!