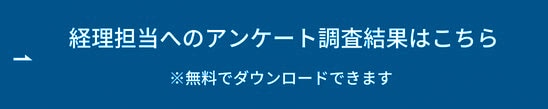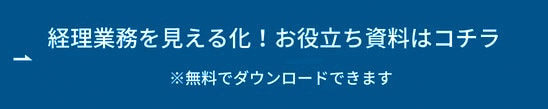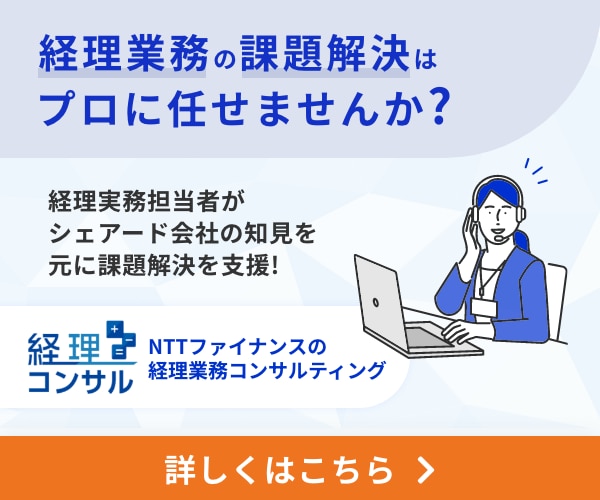若手経理社員への教育で押さえるべき3つのポイント!イマドキ社員の特徴とは?
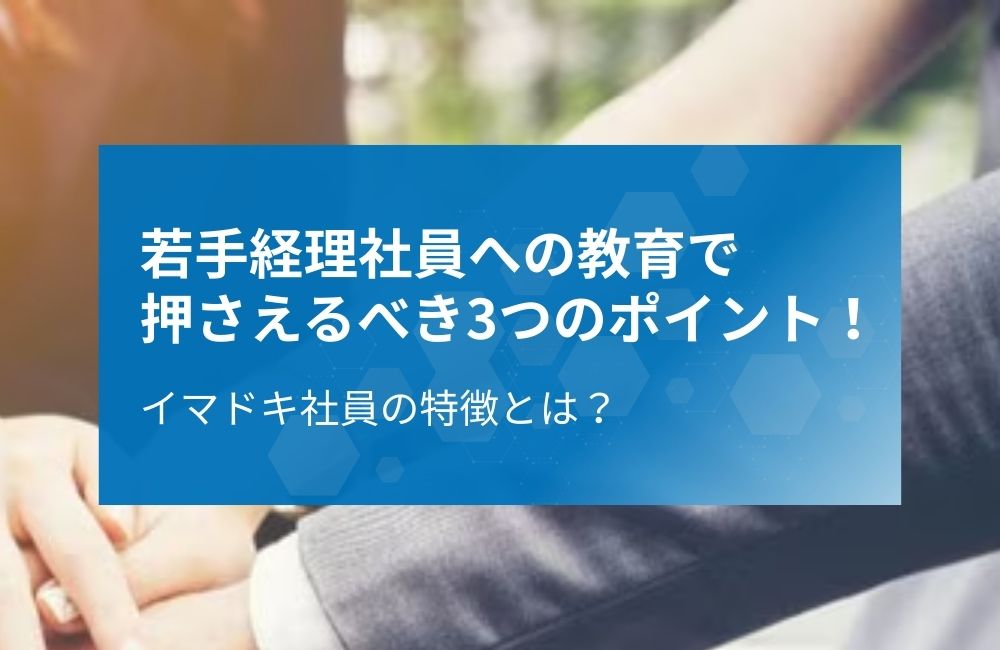
近年入社する若手社員は、デジタルネイティブで情報収入能力に長けている・働く環境の「心地よさ」を重視する傾向があるなどの特徴を持ちます。
これらの特徴をよく理解せず、従来の教育方法のまま指導していると、なかなか思うような効果は得られません。
そこで本記事では、下記の内容を紹介します。
- イマドキの若手社員の特徴5選
- 若手経理社員への教育で失敗しがちなケース
- 若手経理社員への教育で押さえるべき3つのポイント
この記事を読むと、若手社員の教育の仕方で失敗する可能性を減らせますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次[非表示]
イマドキの若手社員の特徴5選

若手経理社員への教育のコツを知る前に、まずは「知っておくべきイマドキ若手社員の特徴」を紹介します。
「JMAM」が公表している意識調査の結果も交えて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考1:JMAM|イマドキ若手社員の仕事に対する意識とは
参考2:JMAM|【イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2022】(前編)
特徴1.失敗を恐れる傾向がある
イマドキの若手社員は、うまくいかないことを恐れてチャレンジを避ける傾向があります。
「失敗したらどうしよう」などという不安から、新しいことに踏み出せないケースも少なくないようです。
このとき「失敗するのは良くない」という考えが社内に浸透していると、若手社員はますます挑戦しづらくなってしまいます。
失敗を恐れずにチャレンジする心と、それを許す環境を提供することが重要です。
特徴2.プライベートを重視する傾向がある
イマドキの若手社員は、仕事よりもプライベートな時間を大切にしたいと考えている傾向が強いです。
例えば、「残業はできる限りしたくない」「飲み会の付き合いをしたくない」などと感じている社員もいます。
プライベートを制約するような発言は、パワハラと言われてしまうリスクもあるため、メリハリをつけて働ける環境を提供することが求められます。
特徴3.働く環境の「心地よさ」を重視する
働く環境の心地よさを重視しているのも、イマドキの若手社員の特徴です。
人間関係や業務量など、自分が無理をしない範囲で仕事をしたいと考えている傾向があります。
「上司ガチャ」といった言葉があるように、特に上司との関係性は軽視できません。
上司として、強く注意すべきシーンも訪れるかもしれませんが、働く環境の「心地よさ」を重視する若手社員も存在することは念頭に置いておきましょう。
特徴4.対面でコミュニケーションを取りたがる
リモートワークが普及する昨今でも、対面でコミュニケーションを取りたがる若手社員は多いです。
その理由としては、「コミュニケーションをとって働く人との関係性をよくしたい」と思っていたり、「なにか相談する際に直接話を聞いてほしい」と感じていたりすることなどが挙げられます。
これに付随して、働く人とのチームワークを重視する傾向があるようです。
若手社員を孤立させることなく、みんなで同じ目標に向かって働ける環境の構築も大切です。
特徴5.情報収集能力に長けている
イマドキの若手社員は、スマートフォンやPCを活用して、必要な情報をすぐに収集できる能力が高いです。
この能力に関しては、デジタルネイティブだからこその特徴とも言えそうです。
|
【デジタルネイティブとは】
インターネットやデジタル技術が生まれた頃から存在し、幼い頃からそれらに囲まれて育ってきた世代を指す。
|
ただし、情報を鵜呑みにしてしまう危険性もあるため、情報の取捨選択は教育してあげる必要があります。
また、SNSにあがるような会社の不祥事などにもとても敏感なので、教育すると同時に上司側のリテラシーも高めることが欠かせません。
上司もSNSリテラシーを高め、不適切な発信や情報拡散を防ぐための対策を講じる必要があります。
若手経理社員への教育で失敗しがちな4つのケース

ここで、若手経理社員への教育で失敗しがちなケースを4つ紹介します。
「自分の常識は通用しない」と考えて教育を実施するくらいが、ちょうど良いかもしれません。それでは、具体的なケースを見ていきましょう。
ケース1.一方的に価値観を押し付けてしまう
多様な価値観を尊重する傾向があるのが、現代の若手経理社員です。したがって、管理職の価値観を一方的に押し付けると反発されたり、最悪の場合は退職したりする可能性もあります。
一方的な押し付けはおこなわず、対面でのコミュニケーションを通じて、互いの価値観を理解し合うことが大切です。
ケース2.上の世代の常識を押し付けてしまう
ケース1に近い内容ですが、上の世代の常識を若手の経理社員に押し付けないことが重要です。
「私はこうしていた」「昔からこうだから」という根拠がない状態で物事を進めると、若手の経理社員から反発を買いやすくなってしまいます。
何かを教える際は、なぜその方法が良いのかしっかりと根拠立てて説明し、納得感を持って仕事に取り組んでもらうようにしましょう。
ケース3.ネガティブなフィードバックを感情でおこなってしまう
若手の経理社員は、ネガティブなフィードバックにとても敏感です。感情で「だからダメなんだ」「もっと考えてやれ」のような叱責は避けるようにしましょう。
愛情を感じられず、ただ感情で物事を言っているように感じられてしまうと、パワハラととらえられてしまうケースもあります。
「どうすればもっと良くなるか」を、若手の経理社員と一緒に考える姿勢が大事です。
とはいえ、何も指摘しないのはむしろ心配になってしまう若手の経理社員もいます。このような社員に対しては、具体的な改善案を提示してあげると安心して業務に取り組んでくれます。
ケース4.個人の特徴を理解せずに他の社員と比較してしまう
イマドキの若手経理社員は、個人の特性や強みを活かしたいと考えている傾向があります。
これを言い換えると「他の人と比べてどうかよりも、個人の強みや良さを引き出してくれるか」が重要ということです。
したがって、明確な基準もなく一律で同じ評価をするのはモチベーション低下の原因になります。
その人の「成長」や「結果に至るまでの過程」を認めて、評価してあげることが重要です。
若手経理社員への教育で押さえるべき3つのポイント

ここからは、若手経理社員への教育で押さえるべきポイントを3つ紹介します。
ポイントを押さえて、より良い教育ができるようにしていきましょう。
ポイント1.会社の理念やビジョンを理解してもらう
イマドキの若手社員は、「なぜそれをやるのか」といった根拠を重視する傾向があります。
そのため、「会社の目指す方向性」や「大事にしている価値観」を若手経理社員に理解してもらうことが重要です。
理念やビジョンを説明して「この仕事をした結果、どこに向かっているのか」を明確にしてあげましょう。目的が明確になると、若手経理社員のモチベーションアップにつながります。
ポイント2.心地良い職場環境であることを伝える
若手経理社員への教育では、心地良い職場環境であることを伝えましょう。
具体的には、
- ミスや業務改善などの仕事の悩みは気軽に相談してOK
- キャリアの相談もOK
などと伝えるイメージです。
若手経理社員は、何かあれば相談したいと考えている傾向にあるため、いわゆる「メンター」がいることをイメージさせてあげましょう。
ただし、プライベートな内容に関しては注意が必要です。プライベートな話題には干渉してほしくない若手経理社員もいるので、個々にあわせてチューニングしましょう。
ポイント3.定期的なフィードバックの機会を設ける
若手経理社員の多くは、自分の成長を実感したいと考えています。成長を実感させてあげるには、定期的な面談の実施が効果的です。
上司から直接フィードバックをもらうことで、自己成長の実感につながります。うまくいった取り組みは褒めて、改善点は具体的に伝えることが大切です。
できることなら評価や努力値を「数値化」して、目に見えてわかる状況を作ると、モチベーション高く働いてくれやすくなります。
なお、経理担当のみなさんは、若手経理社員の教育以外にも悩みがあるのではないでしょうか。
例えば、「業務の効率化ができていない」「属人化が進んでいて担当者を変えられない」などがよくある悩みです。
次章では、上記の悩みの解決方法を紹介しますので、よろしければこのまま続きをご覧ください。
【コラム】経理担当が抱える他の悩み

この章では、教育面以外で経理担当が抱えがちな悩みを2つ紹介します。
解決策も紹介しますので、取り組みやすいものからチャレンジしてみてください。
悩み1.経理業務の効率化が進んでいない
「経理業務の効率化が進んでいない」のは、経理担当が抱えるよくある悩みです。
例えば、いまだに紙の文書を多く使用していたり、請求情報や財務データなどをExcelの表で手打ちで管理していたりします。
DX化が進んでいないことに付随して効率化が進まないため、どうしても残業時間も増えてしまいます。
下記の記事では、経理DXのメリットや進め方を解説していますので、効率化を叶えたい方はぜひご覧ください。
また当サイトでは、経理担当者にアンケートをおこなって得られた「経理部門の本音」がわかる資料を無料配布しています。
現場の経理担当がどのような悩みを抱えているかを把握したい方は、下記のバナーをクリックのうえお気軽にダウンロードしてください。
\普段は❝なかなか言えない❞経理部門の本音がここに/
▲1分でダウンロード完了
悩み2.属人化しやすく担当者を代えられない
経理業務が属人化しており、担当者を代えられないこともよくある悩みの一つです。
一部の従業員に業務が集中する結果、引き継ぎ用の資料作成や教育のための時間が取れず、負のループに陥っているケースもみられます。
この状態で担当者が退職したり怪我や病気で職場を離れたりすると、業務が進まなくなる可能性も否めません。
属人化で業務がブラックボックス化した状態だと、経理担当による不正リスクも高まります。
【属人化とブラックボックス化の違い】
※属人化を放置していると、ブラックボックス化が進んでしまう |
当サイトでは、ブラックボックス化しがちな経理業務をどうすれば見える化できるかをまとめた資料を無料で配布しています。
ビジネスへの悪影響を未然に防ぎたいと考えている方は、下記のボタンをクリックのうえお気軽に資料をダウンロードしてください。
\ブラックボックス化した経理を健全化する方法を網羅!/
若手経理社員の教育はコツを知って失敗を避けよう

【本記事のまとめ】
|
イマドキの若手社員は、根性論や精神論のような教育方針を嫌う傾向にあり、昔のやり方ではなかなか通用しません。
イマドキの若手社員の基準にすべて合わせる必要はありませんが、考え方を尊重しつつ教育を進めていきましょう。
なお当サイトでは、経理担当に向けた記事を多数公開しています。気になる記事があれば、ぜひチェックしてみてください。