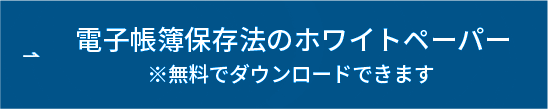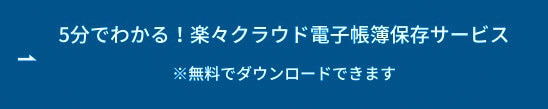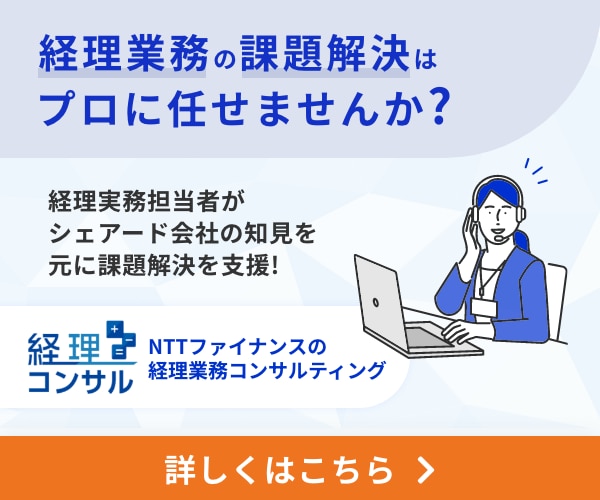電子帳簿保存法で必要な対応とは?2つのケースに分けて完全ガイド
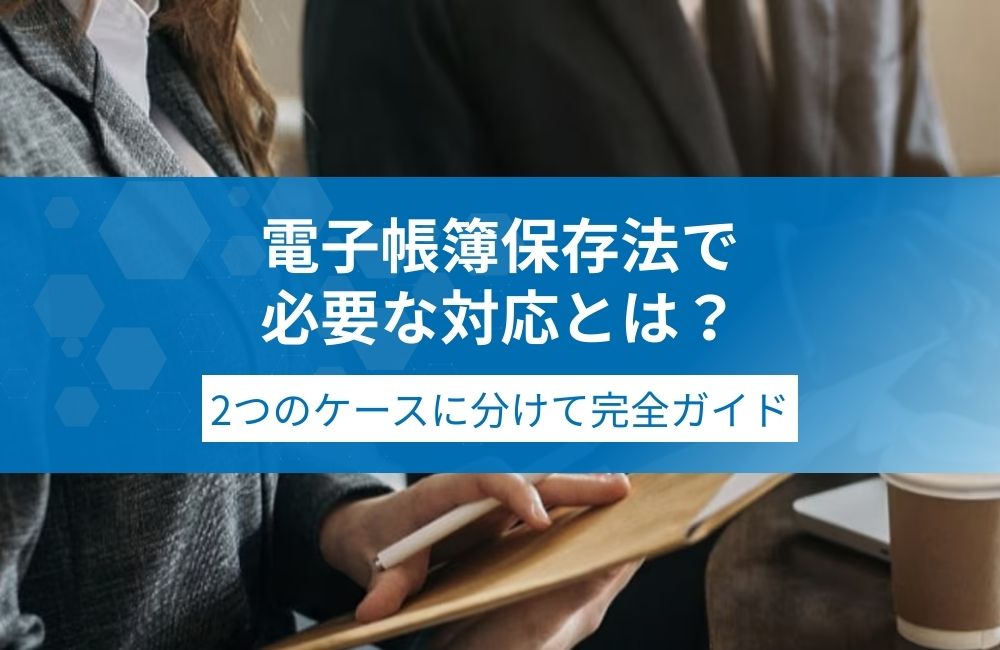
電子帳簿保存法が改正され、インターネットを介して取引した情報は、紙ではなく電子データで保存することが義務付けられました。
適切な形での保存ができていない場合、罰則を科せられるリスクもあるため、電子帳簿保存法への正しい理解が欠かせません。
そこで本記事では、電子帳簿保存法で必要な対応を、
- 電子データで受け取る場合
- 紙で受け取る場合
の2つに分けて解説します。
なお当サイトでは、電子帳簿保存法の概要や必要な対策についてまとめた資料を無料配布しています。
特に「電子取引制度」に関しては、2024年1月以降すべての事業者で対応が必要になったため、対策を図りたい方は下記のバナーからお気軽に資料をダウンロードしてください。
▲1分でダウンロード完了!
目次[非表示]
2024年1月から電子取引情報は電子データでの保存が義務付けられる

電子帳簿保存法では、国税関係の帳簿や書類に関して「電子データでの保存」を認めています。
なかでも2022年におこなわれた法改正により、電子取引でやり取りした情報は電子データでの保存が義務付けられました(※)。
種類 | 例 | 紙で保存 | 電子データで保存 |
国税関係帳簿 |
| ○ | ○ |
国税関係書類 |
| ○ | ○ |
電子取引情報 |
| × ※2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、 紙での保存はNGに。 | ○ |
上記の表に記載があるとおり、国税関係帳簿と国税関係書類については引き続き紙での保存も可能です。
一方で、電子取引情報に関しては紙でなく電子データで保存しなければならず、各事業者には法律に則った正しい対応が求められています。
電子取引とは、電子データを用いてやり取りした取引情報(請求書・領収書など)のことです。
下記の記事では、電子取引の保存要件から対応方法まで網羅的に解説していますので、あわせてご覧ください。
電子帳簿保存法で必要な対応を2つのケースに分けて解説

ここからは、電子帳簿保存法で必要な対応を下記2つのケースに分けて解説します。
さっそく、ひとつずつ見ていきましょう。
ケース1.電子データで受け取る場合に必要な6つの対応
電子データで受け取る場合に必要な対応は、次の6つです。
- 自社の取引状況を把握する
- 電子取引した情報の保存方法を決める
- 電子データを保存する場所を決める
- 電子データで経理に回す業務フローを作成する
- システムの関係書類を備え付ける
- 従業員や取引先に周知して運用を開始する
2024年1月以降、電子データで受け取る場合は紙での保存が無効となってしまうため、データ保存するための正しい知識が欠かせません。
それでは、順番に解説します。
対応1.自社の取引状況を把握する
まずは、現時点での取引状況を整理することから始めます。具体的な確認事項は、次のとおりです。
確認事項 | 概要 | 例 |
取引書類 | どのような書類を電子取引しているのか | 請求書、領収書 |
授受方法 | どのような方法で書類を受け取っているのか | 電子メール、EDI取引 クラウド取引 |
保存場所 | 書類はどこに保存しているのか | クラウドシステム 自社サーバー |
件数 | 何件くらい書類を受け取っているのか | 200件/月 |
すべての書類をいきなり対応するのは現実的でないため、経理業務への影響が大きい「請求書」と「領収書」から取り組むのがおすすめです。
請求書と領収書は、経理業務から支払い業務へとつながっているため、優先して取り組んだほうが効果を出しやすいという側面もあります。
対応2.電子取引した情報の保存方法を決める
電子取引データを保存する際は、改ざん防止策として下記4つのうちいずれかの措置をとる必要があります。
|
参考:電子取引データ|国税庁
タイムスタンプとは、付与された時刻以降に文書が改ざんされていないことを証明できる電子的なスタンプです。
つまり、文書にタイムスタンプが押されていれば、その時刻以降に文書が改ざんされていないことを簡単に確認・証明できます。
なお、データを改ざんできないクラウドシステムを利用する場合、タイムスタンプを付与しなくても電子データで保存することが可能です。
下記の記事でタイムスタンプの仕組みや利用手順をまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
対応3.電子データを保存する場所を決める
続いて、クラウドシステムや自社サーバーなど、電子データをどこで保存するか決めます。
電子データを保存する際の注意点は、「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目で検索できる状態を確保しなければならないことです。
具体的には、次のような方法で検索機能を確保することになります。
|
【検索機能を確保したうえで電子データを保存する方法】
|
検索機能の確保は、規則的なファイル名をつけて保存したりExcelで索引簿を作成したりすることで、自社での対応も不可能ではありません。
国税庁のサイトでも、「規則的なファイル名を付ける方法」や「索引簿を作成する方法」の例を公表しています。
参考:電子取引データ|国税庁
しかし、自社での対応は運用・管理面で負担がかかってしまう点がデメリットです。したがって、運用負担を減らすなら「検索要件に対応したクラウドシステム」の活用がおすすめです。
なお下記の記事では、電子帳簿保存法におけるファイル名の「記載例」を紹介していますので、あわせてご覧ください。
対応4.電子データで経理に回す業務フローを作成する
電子データを紙に印刷してから経理に回していた企業は、電子データのまま経理に回す業務フローを新たに作成しましょう。
このとき、一連の業務フローを見直す必要が出てくるため、
- 上長の確認、承認方法はどうするのか(例:メール・システム)
経理への回付方法はどうするのか(例:メール・システム)
など、上長や部門担当者とも協議しつつ、継続して運用できる体制を構築することが大切です。
対応5.システムの関係書類を備え付ける
電子取引した情報をシステム上に保存する際は、「システムの使い方がわかる関係書類」を備え付けておく必要があります。
次のような関係書類を備え付け、画面・書面にわかりやすい状態で速やかに出力できるよう準備しておきましょう。
|
【システムの関係書類の例】
|
対応6.従業員や取引先に周知して運用を開始する
円滑に運用を進めるために、従業員や取引先に対して事前に周知・説明を済ませておきましょう。
従業員へは、事務処理規程などを用意して「電子取引に関するルール」を共有しておく必要があります。
紙でのやり取りから電子取引に切り替えてくれそうな企業があれば、この機会に依頼してみるのも良いでしょう。
ただし、電子取引への切り替えが難しい場合に押し付けるのはNGです。
ケース2.紙で受け取る場合に必要な5つの対応
紙で受け取る場合に必要な対応は、次の5つです。
- スキャンして保存する
- スキャナ保存制度の要件を満たした機器やシステムを用意する
- 国税庁の資料をもとに規定などを備え付ける
- スキャナ保存したデータで経理に回す業務フローを作成する
- 従業員や取引先に周知して運用を開始する
自社での対応をイメージしつつ、チェックしてみてください。
対応1.スキャンして保存する
電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」を活用すれば、紙で受け取った書類をデータ保存したあとに原本を破棄できます。
仕訳入力する前にスキャンし、電子データを見ながら仕訳入力することで、電子取引と同じフローで業務を回せます。
なお、業務フローをより効率化したいのであれば、自社の会計システムと連携できるサービスの活用がおすすめです。
会計システムと連携することで、仕訳の自動入力が可能となり、大幅な業務効率化につながります。
対応2.スキャナ保存制度の要件を満たした機器やシステムを用意する
スキャナ保存制度では、スマートフォンやデジカメで撮影した画像も対象としています。
しかし、スキャナ保存する際は下記の要件を満たした機器やシステムを用意しなければなりません。
|
【スキャナ保存する際に満たすべき要件】
|
※資金や物の流れに直結しない「一般書類」を保存する場合には、グレースケール画像でも可
なお、クラウドシステムのなかには、スキャナ保存を代行してくれるサービスも存在します。
自社でのスキャン作業を削減したい場合、電子帳簿保存法に対応したサービスを活用し、「スキャナ保存を代行してもらう」のもひとつの手です。
対応3.国税庁の資料をもとに規程などを備え付ける
スキャナ保存制度の要件のひとつに、「入力期間の制限」があります。
「入力期間の制限」には、
- 早期入力方式
業務処理サイクル方式
の2種類があり、それぞれ定められた期間までにスキャンして電子データ保存しなければなりません。
種類 | 概要 |
早期入力方式 | 書類の受領後、おおむね7営業日以内に電子化して保存する |
業務処理サイクル方式 | 「月締め」で書類を整理し、帳簿を締めるタイミングからおおむね7営業日以内に電子化して保存する |
上記のうち「業務処理サイクル方式」を選ぶ場合、スキャナ保存制度の要件を満たすために、
- スキャナによる電子化保存規程
国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
を作成する必要があります。
国税庁から参考資料が出ていますので、「業務サイクル方式」を選ぶ場合は必ず規程などを作成するようにしましょう。
対応4.スキャナ保存したデータで経理に回す業務フローを作成する
これまで紙の書類で経理に回していた企業は、「スキャナ保存したデータで経理に回す業務フロー」を作成する必要があります。
スキャナ保存したデータで上長承認や経理への回付をおこなえば、企業のペーパーレス化やテレワーク化にも効果的です。
また、クラウドシステムのなかには、書類の受領や支払い業務まで代行してくれるサービスもあります。
一気に業務効率化を進めたい企業は、この機会に便利なサービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
対応5.従業員や取引先に周知して運用を開始する
円滑に運用を進めるために、従業員や取引先に対して事前に周知・説明を済ませておきましょう。
従業員へは、事務処理規程などを用意して「スキャナ保存に関するルール」を共有しておく必要があります。
紙でのやり取りから電子化に切り替えてくれそうな企業があれば、この機会に依頼してみるのも良いでしょう。
ただし、電子化が難しい場合に押し付けるのはNGです。
電子帳簿保存法に対応するならクラウドシステムの活用がおすすめ

前提として、クラウドシステムを利用せずに電子帳簿保存法の要件を満たすことも可能です。
しかし、自社だけの対応だと導入・運用の負担が大きく「無事に要件を満たせているのか」不安を感じるケースも少なくありません。
そこでおすすめなのが、電子帳簿保存法に対応したクラウドシステムの活用です。
例えば、「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、電子帳簿保存法のすべての保存区分に対応しているため、電子帳簿保存法の内容を深く理解していなくても法令に準拠した税務処理業務が可能です。
|
【楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloudが持つ強みの例】
|
「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、初期費用0円・月額900円からと低価格で利用できます。
サービスの詳細が気になる方に向けて、5分で理解していただける資料をご用意しましたので、下記のボタンよりお気軽にダウンロードしてください。
\サービスの特長から導入の流れまでわかる!/
▲1分でダウンロード完了!
電子帳簿保存法に関してよくある2つのQ&A

電子帳簿保存法でよくある質問と、その回答をまとめました。
気になったものがあれば、ぜひチェックしてみてください。
Q1.電子帳簿保存法の対象となる文書は?
電子帳簿保存法でデータ化が認められているのは、「国税関係帳簿」と「国税関係書類」です。
種類 | 例 | 紙で保存 | 電子データで保存 |
国税関係帳簿 |
| ○ | ○ |
国税関係書類 |
| ○ | ○ |
電子取引情報 |
| × ※2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、 紙での保存はNGに。 | ○ |
加えて、電子データでやり取りした情報は、2024年1月以降、紙ではなく電子データでの保存が義務付けられました。
当サイトでは、「電子帳簿保存法の概要」や「すべての事業者が実施すべき4つの対策」などについてまとめた資料を無料配布しています。
ご興味があれば、下記のボタンからお気軽にダウンロードしてください。
\保存要件の概要はコレひとつでOK!/
▲1分でダウンロード完了!
Q2.電子帳簿保存法の対象となる事業者は?
電子帳簿保存法は、所得税法や法人税法などで称される保存義務者(帳簿や書類の備え付けが求められる者)が対象です。
つまり法人・個人に関わらず、ほぼすべての事業者が対象となります。詳しくは下記の記事で紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
電子取引制度への対応を早急に進めよう

|
本記事のまとめ
|
2024年1月以降、電子データで受け取った「電子取引情報」は、紙ではなく電子データでの保存が必要となりました。
すべての事業者が対象となりますので、電子取引制度への対応ができていない方は早めの対策を進めましょう。
なお、電子帳簿保存法への対応を効率的かつ確実に実施するなら、クラウドシステムの活用がおすすめです。
例えば、「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、電子帳簿保存法に完全対応しているため、導入企業は電子帳簿保存法への対応が容易になります。
クラウドシステムのなかには、請求書など一部の書類のみ電子帳簿保存法に対応しているサービスも存在します。
一方で、「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、請求書以外の帳票類(契約書・見積書・領収書など)にも幅広く対応できる点が強みです。
サービス詳細について5分でわかる資料を無料配布していますので、下記のボタンからお気軽にダウンロードしてください。
▲1分でダウンロード完了!