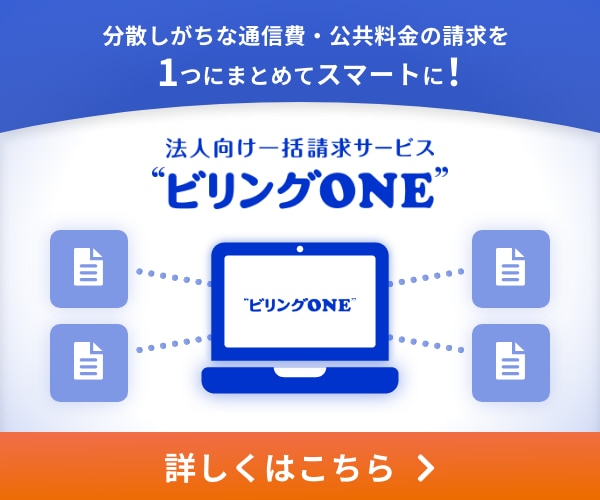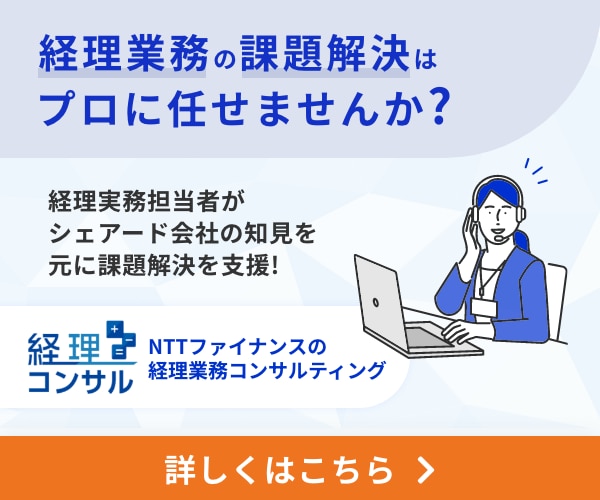【例文あり】請求書をメール送付する際の注意点は?基本ルールやメリットなども紹介
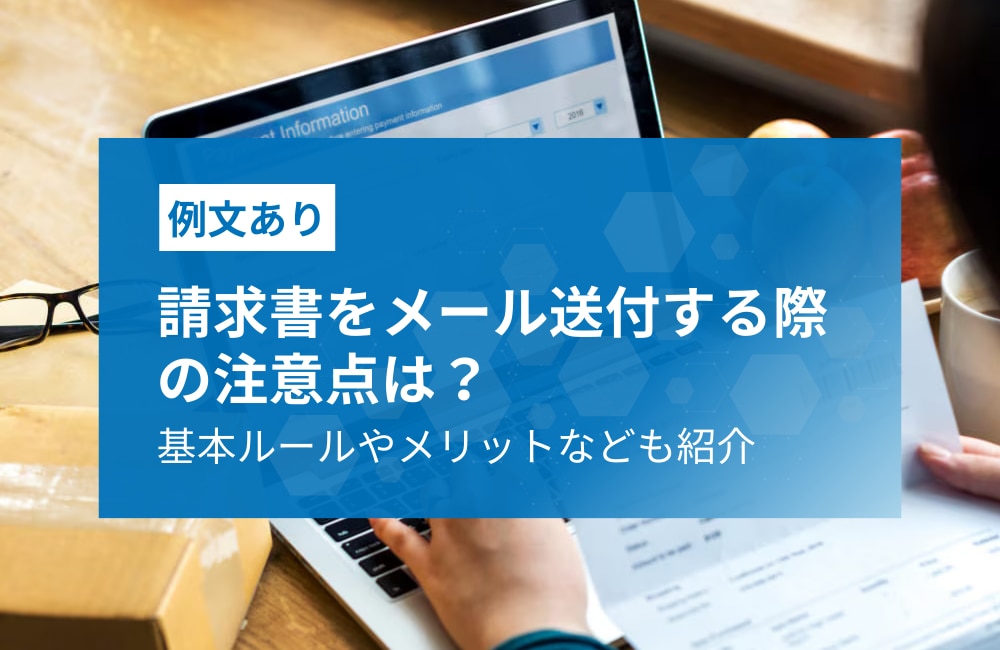
請求書のメール送付は法人・個人を問わず、取引を行う事業者にとって切っても切り離せない存在です。取引先との信頼関係にも関わるため、基本的なルールやマナーを押さえておくことが欠かせません。
本記事では、主に下記の内容を紹介します。
|
基本ルールから注意しておきたい点、効率化につながるサービスまで網羅的に解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
「請求書のメール送付文例」を今すぐ知りたい人は、下記をクリック!
>>>請求書のメール送付の文例を3つ紹介<<<
目次[非表示]
請求書のメール送付前に確認すべき4つの基本ルール

請求書をメールで送付する際は、事前に確認しておくべき必須のルールがあります。
上記のルールを守ることで、取引先との信頼関係を保ちながらスムーズな請求業務を実現できます。
ルール1.取引先の事前承諾を得る
請求書をメールで送付する前に、必ず取引先の承諾を得ることが必要です。法的には請求書のメール送付に問題はありませんが、取引先によっては紙での送付を原則としている企業もあります。
事前確認を怠ると取引先の業務フローに支障をきたし、信頼関係に悪影響を与える可能性も否めません。
初回取引時や担当者が変更になった際は、必ず送付方法について確認を取りましょう。確認時には、送付先のメールアドレスやCC設定も併せて聞いておくと安心です。
ルール2.PDFファイル形式で送付する
請求書をメールで送付する際は、PDFファイル形式を使用することが原則です。WordやExcelファイルをそのまま送付すると、受信者が誤って内容を編集してしまうリスクがあります。
PDFファイルは編集が困難で、フォーマットが崩れる心配がほとんどありません。
また、どのデバイスでも同じ表示が可能なため、取引先が確実に内容を確認できます。作成したWordやExcelファイルは「PDFとして保存」機能を使って変換し、元のファイルとは別に保管しておくことが大切です。
ルール3.原本郵送の必要性を確認する
メールで請求書を送付した後に、紙の原本も郵送する必要があるかを事前に確認しましょう。企業によっては、メール送付は確認用として扱い、正式な処理には紙の原本が必要な場合があります。
原本郵送が必要な場合は、メール本文にその旨を記載しておくと親切です。「追って原本を郵送いたします」などの一文を加えることで、取引先の混乱を防げます。
逆に原本郵送が不要な場合は、「電子データでの保管をお願いします」と明記しておくと良いでしょう。
ルール4.押印の要否を確認する
請求書への押印については法的な義務はありませんが、取引先が押印を求める場合があります。メール送付を行う前に、押印の必要性について確認しておくことが欠かせません。
押印が必要な場合は、紙の請求書に押印してからスキャンしてPDF化する方法と、電子印鑑を使用する方法があります。
電子印鑑のほうが効率的ですが、取引先が認めない場合もあるため注意が必要です。押印形式についても事前に相談し、双方が納得できる方法を選択しましょう。
【ケース別】請求書のメール送付の文例3パターン

請求書をメールで送付する際の文面は、状況に応じて適切に使い分けることが必要です。
ここでは、よくある3つのケースに分けて実際に使える文例をご紹介します。
文例1.PDFのみ送付で原本は郵送しない場合
PDFのみ送付で、原本は郵送しない場合の文例を紹介します。
件名:【請求書】2025年7月分請求書送付のご案内|株式会社○○ 株式会社△△ 経理部 ●●様 いつもお世話になっております。 株式会社○○の経理部、××と申します。 2025年7月分の請求書をお送りいたします。 添付ファイルにてご確認をお願いいたします。 【添付内容】 ・請求書(No.2024-1201).pdf 1通 【請求内容】 ・請求金額:¥123,456(税込) ・お支払期日:2025年7月31日 ・振込先:○○銀行△△支店 普通預金 1234567 なお、こちらの請求書は電子データでの保管をお願いしており、原本の郵送は実施しておりません。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
紙の原本を省略したいときや、すぐに請求書を届けたいときに便利なパターンです。取引先に配慮した一文を添えることで、スムーズなやりとりが可能になります。
文例2.PDFと原本の両方を送付する場合
PDFと原本の両方を送付する場合の文例は、下記のとおりです。
件名:【請求書】2025年7月分請求書送付・郵送のご案内|株式会社○○ 株式会社△△ 購買部 ●●様 平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。 株式会社○○の営業部、××です。 2025年7月分の請求書を添付にてお送りいたします。 併せて、請求書の原本も本日郵送いたしましたので、ご査収のほどよろしくお願いいたします。 【添付内容】 ・請求書(No.2024-1201).pdf 1通 【請求内容】 ・請求金額:¥987,654(税込) ・お支払期日:2025年7月31日 原本は明日到着予定でございます。 万が一、添付ファイルが開けない場合や、原本が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。 |
「データはすぐにほしいが、保管のために原本も必要」という相手にも対応できる便利なケースです。両方の送付を明記することで、混乱を防げます。
文例3.初回メール送付で丁寧な挨拶を含める場合
初回メール送付で丁寧な挨拶を含める場合の文例は、次のとおりです。
件名:【初回・請求書】2025年7月分請求書送付のご案内|株式会社○○ 株式会社△△ 経理部 ●●部長 拝啓 師走の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 この度、弊社では業務効率化の一環として、請求書の送付方法をメール送付に変更させていただきました。 事前にご了承をいただいておりましたとおり、2025年7月分の請求書を電子データにてお送りいたします。 【添付内容】 ・請求書(No.2024-1201).pdf 1通 【請求内容】 ・請求金額:¥555,000(税込) ・お支払期日:2025年7月31日 今後ともメール送付での対応を予定しておりますが、ご不都合がございましたらお申し付けください。 何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具 |
初めてメールで請求書を送るときや、送付方法を切り替える場面で特に役立つ文面です。丁寧なご案内を添えることで、相手の安心感につながります。
請求書のメール送付時に守るべき4つの注意点

請求書をメールで送付する際は、確実に相手に届いたうえで適切に処理されるよう細心の注意を払う必要があります。次に示す注意点を守ることで、送付ミスやトラブルを防止できます。
順番にみていきましょう。
注意点1.わかりやすい件名をつける
メールの件名は、受信者が一目で請求書メールだと判断できるよう工夫することが大切です。取引先によっては月末に多くのメールが届く場合があるため、件名が曖昧だと他のメールに埋もれてしまう可能性があります。
▼効果的な件名の例 【請求書】2025年7月分請求書送付のご案内|株式会社○○ |
【請求書】の文字を最初に配置し、対象月と会社名を含めることで、内容と送信者がすぐに伝わりやすい点がポイントです。件名に日付や金額を含める企業も多く、相手の業務効率向上にも貢献できるます。
注意点2.適切なファイル名をつける
添付する請求書PDFには、内容がわかりやすいファイル名をつけることが不可欠です。「請求書.pdf」のような汎用的な名前では、取引先がファイルを管理する際に困ってしまいます。
▼推奨されるファイル名の形式 20250701_請求書_株式会社○○_123456円.pdf |
日付、書類種別、会社名、金額を含めるファイル名がおすすめです。この形式なら、取引先が後からファイルを検索する際にも便利になります。
電子帳簿保存法の要件も考慮し、統一されたルールでファイル名を作成する習慣をつけましょう。
注意点3.添付ファイルの存在を本文で明記する
メール本文には、請求書ファイルを添付していることを明確に記載しましょう。添付ファイルの存在がわからないと、受信者が見落としてしまう可能性があります。
▼本文への記載例 請求書(ファイル名:20250701_請求書_○○.pdf)を添付しております。 |
本文には具体的なファイル名も含めて記載しましょう。
また、請求金額や支払期日などの中核となる情報も本文に記載しておくと、添付ファイルを開く前に概要を把握できるため親切です。
注意点4.送信前に宛先と内容を再確認する
メール送信前には、必ず宛先アドレスと添付ファイル、本文内容を再確認しましょう。誤送信は取引先の信頼を失うだけでなく、情報漏洩のリスクもともないます。
確認すべき項目は下記のとおりです。
▼確認項目
|
可能であれば、送信前に同僚にチェックしてもらう仕組みを作ると安心です。送信後は、相手に届いたかを確認する連絡も入れるとより確実になります。
請求書のメール送付で得られる4つのメリット
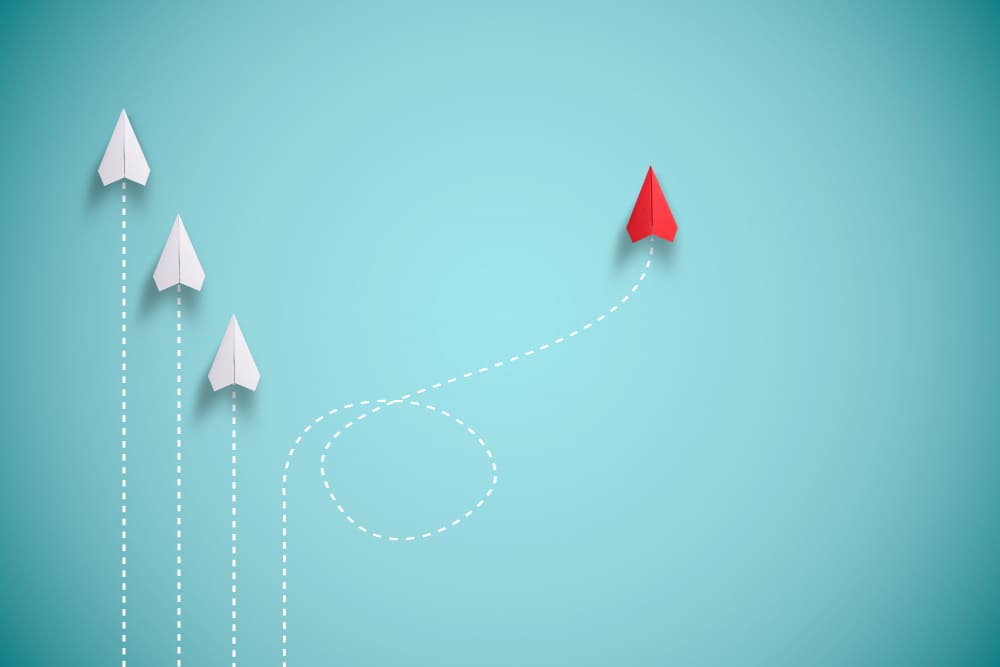
請求書のメール送付には、従来の郵送方法と比較して多くのメリットがあります。
メリットを理解することで、業務効率化の具体的な効果を把握できます。
メリット1.郵送コストと作業時間が削減できる
請求書のメール送付により、印刷代・用紙代・封筒代・切手代などの直接的なコストを大幅に削減できます。月に100通の請求書を発行する企業の場合、郵送費だけで年間約10万円以上の節約が可能です。
加えて、作業時間の短縮効果も見逃せません。印刷や封入、宛名書きや郵便局への持参といった一連の作業が不要となり、担当者は他の価値ある業務に時間を充てられます。郵送の場合は1時間以上かかる作業も、メール送付なら数分で完了することも珍しくありません。
メリット2.送付ミスや紛失リスクが防げる
メール送付では、宛先間違いや郵送事故による紛失リスクの削減が可能です。
郵送の場合、住所の記載ミスや配達中のトラブルにより請求書が届かない可能性があります。一方で、メールなら送信履歴で確実に送付を確認できます。
また、誤送信があった場合でも、パスワード設定により情報漏洩を防止できる点も注目すべき要素です。郵送で間違った宛先に送付してしまうと回収が困難ですが、メールなら追加の注意喚起メールを送ることで被害を最小限に抑えられます。
デジタル化により、ヒューマンエラーによるリスクを効果的に軽減できる点もメリットです。
メリット3.即座に修正対応ができる
請求書に間違いが発見された場合、メール送付なら迅速に修正版を送付できます。郵送では再印刷から投函まで最低でも1日はかかりますが、メールなら修正後すぐに再送信が可能です。
迅速な対応は、取引先との関係維持に欠かせません。ミスに気付いた段階で即座に謝罪と修正版の送付を行えるため、相手に与える迷惑を最小限に抑えられます。
支払期日が迫っている場合でも、メール送付なら期限内に正しい請求書を届けられて、入金の遅れによる混乱などを防ぐことができます。
メリット4.電子データで管理がしやすくなる
請求書の管理が格段に効率的になります。電子データにしていると「検索機能」を使って特定の請求書を瞬時に見つけられるので、紙の書類のように保管場所に困ることもありません。
データベースとの連携も容易で、会計ソフトへの取り込みや売上分析などの作業効率が向上します。
また、テレワーク環境でも請求書の確認や管理が可能となり、働き方改革にも効果抜群です。バックアップも簡単に取れるため、災害時のリスク管理としても有効な手段といえます。
請求書のメール送付における「電子帳簿保存法」に対応した3つの保存要件

請求書をメールで送付した場合、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当するため、「真実性の確保」と「可視性の確保」が必要です。
参考:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】Ⅱ 適用要件【基本的事項】
適切な保存を行うための基本的なポイントを確認しましょう。
要件1.検索可能なファイル名で保存する
電子帳簿保存法では、保存した請求書データを「取引年月日」「取引先名」「取引金額」の3つの項目で検索できる状態にしておく必要があります。最も簡単な方法は、これらの情報をファイル名に含めることです。
▼推奨されるファイル名の例 20250701_株式会社○○_123456 |
この形式なら、税務調査の際に提示を求められても迅速に資料の提示が可能です。
フォルダ分けも併用し、年月別や取引先別に整理しておくと、さらに管理が効率的になります。統一されたルールを作成し、全社で徹底することが欠かせません。
要件2.改ざん防止措置を講じる
電子データの真実性を確保するため、改ざん防止措置を講じる必要があります。
具体的な方法として、タイムスタンプの付与・訂正削除履歴が残るシステムの使用・改ざん防止に関する事務処理規程の制定などがあります。
多くの企業では、電子帳簿保存法対応のクラウドサービスを利用して要件を満たしています。これらのサービスは自動的にタイムスタンプが付与され、改ざん防止機能も備えているため便利です。
自社でシステムを構築する場合は、訂正や削除を実施した際の履歴が確実に残る仕組みを整備することが求められます。
要件3.見読性を確保した環境を整える
保存した請求書データを税務調査などの際に、速やかに画面表示または書面に出力できる環境を整備する必要があります。これを「見読性の確保」と呼び、電子帳簿保存法の中核となる要件の一つです。
具体的には、保存したデータを表示するためのパソコンやモニター、プリンターなどの機器を常時使用できる状態にしておくことが求められます。
また、データの保存場所やアクセス方法を明確にし、担当者以外でも必要時に閲覧できる体制を整備しましょう。クラウドサービスを利用している場合は、インターネット接続環境の確保も必須の要素です。
なお、電子帳簿保存法に対応するなら、専用システムの導入がおすすめです。例えば、NTTファイナンスの「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、電子帳簿保存法のすべての保存区分に対応したサービスです。
本サービスを導入することで、電子帳簿保存法について深く把握していなくても法令に準拠した税務処理業務が可能になります。
初期費用0円・月額基本料900円からと低価格で利用できる「楽々クラウド電子帳簿保存サービス」の詳細は、下記のバナーをクリックのうえ資料をダウンロードしてご確認ください。
\サービスの特長から導入の流れまでわかる!/
請求書を1枚にまとめるなら「法人"ビリングONE"」がおすすめ
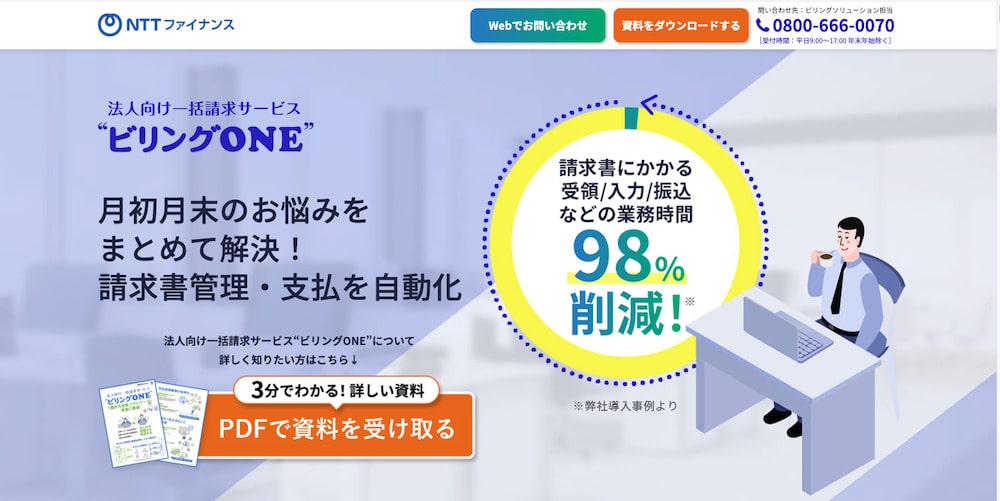
メールの送付も含めて請求書業務そのものを効率化したい方には、NTTファイナンスの「法人"ビリングONE"」がおすすめです。
「法人"ビリングONE"」は、支払い期日が異なる請求書をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 要問い合わせ |
対象の請求書 | 通信費・公共料金・その他 |
複数の拠点ごとにバラバラ届く請求書や、支払い期日が異なる請求書(通信費・公共料金・その他)を1枚の電子請求書(紙請求も可)にまとめることで、支払い処理を1回にできます。
従来の支払い作業・開封・保管の負担を軽減できるため、複数枚届く請求書や何通も届くメールの処理にかかっていた経理業務の大幅な効率化が可能です。
インボイス制度にも対応している「法人"ビリングONE"」の詳細は、下記からサービス資料をダウンロードのうえご確認ください。
\請求書管理・支払いを自動化できる!/
請求書のメール送付に関するよくある質問

最後に、請求書をメールで送付する際によくある質問とその回答を紹介します。
質問1.メールを送付するタイミングはいつが良い?
請求書をメールで送付するタイミングは、取引先の締め日に合わせることが基本です。多くの企業では月末締めとなっているため、翌月の1~5日以内に送付を求められる場合が多い傾向があります。
ただし、取引先によって締め日が異なるため、契約時に必ず確認しておかなくてはなりません。取引先の営業日の午前中に送付すると、相手が確認しやすく処理もスムーズに進みます。
質問2.メールの送付後のフォローアップやリマインドはどうすればいい?
請求書のメール送付後は、3日~5日程度で受信確認の連絡を入れると安心です。返信がない場合は「請求書の件でご確認いただきたいことがございます」といった件名で、丁寧にフォローメールを送りましょう。
頻繁に連絡すると相手に迷惑をかけるため、1度送った後は再度3日程度空けるなど、適度な頻度を心がけることが大切です。
請求書のメール送付は正しいルールに沿って実施しよう
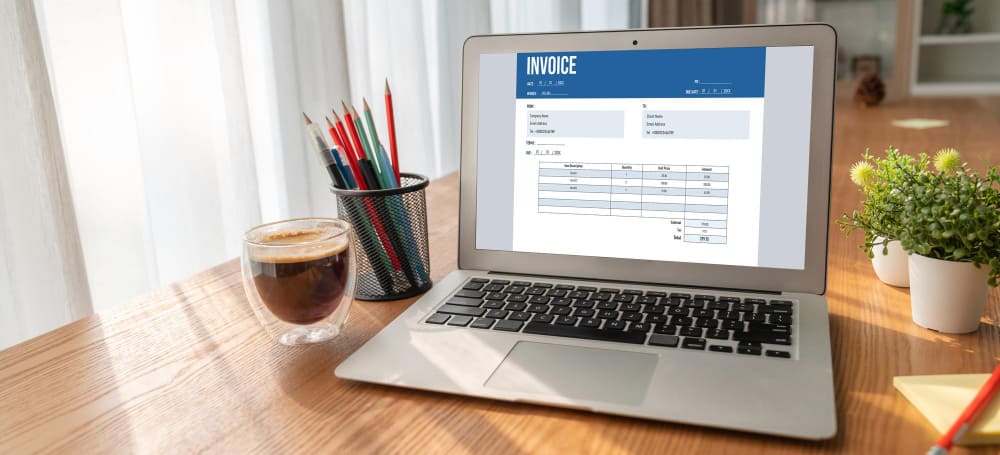
【本記事のまとめ】
|
請求書のメール送付には、「原則PDF化」や「取引先との事前のすり合わせ」など、外せないポイントがあります。加えて「送る際のお作法」や「電子帳簿保存法への対応」などへの配慮も必要であり、ただ添付して送れば良いものでもありません。
本記事を参考に要点を把握したうえで、請求書の正しい送り方を身につけましょう。なお、請求書の送付そのものを自動化し、経理業務全体の効率化を求めるのもおすすめです。
例えば、NTTファイナンスの「回収代行サービス」は顧客への請求を自動化できるサービスです。導入企業は請求情報を入力するだけで、NTTファイナンスが代わりにエンドユーザーへ請求を行います。30種類以上の決済手段を提供しており、法人・個人にかかわらず利便性の高い選択肢を提供している「回収代行サービス」の詳細は、下記のバナーをクリックのうえ、資料をダウンロードしてご覧ください。
\ 全国対応の営業体制で、万全のフォロー! /