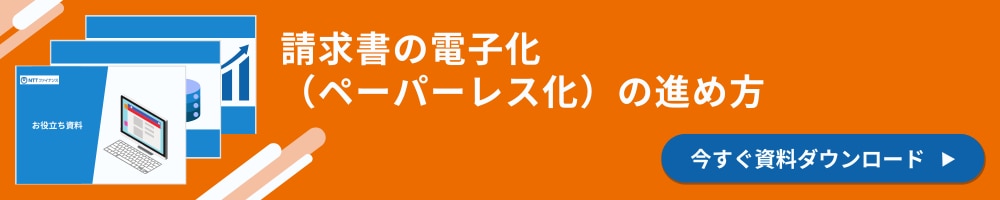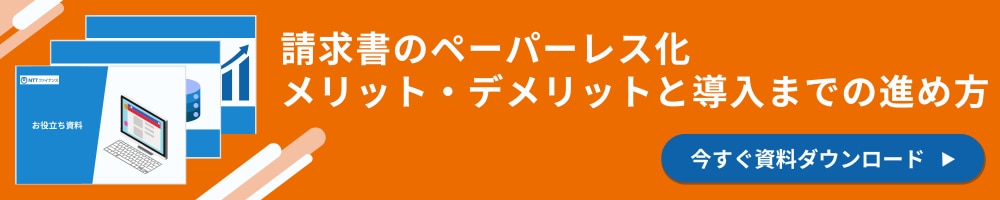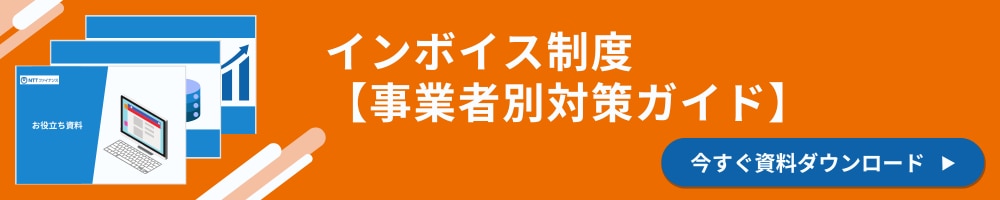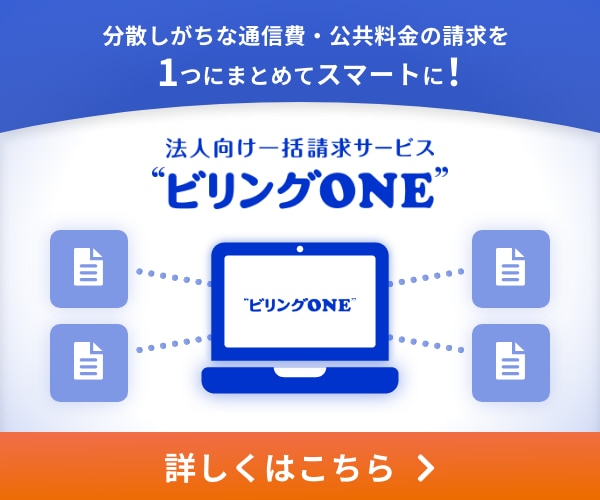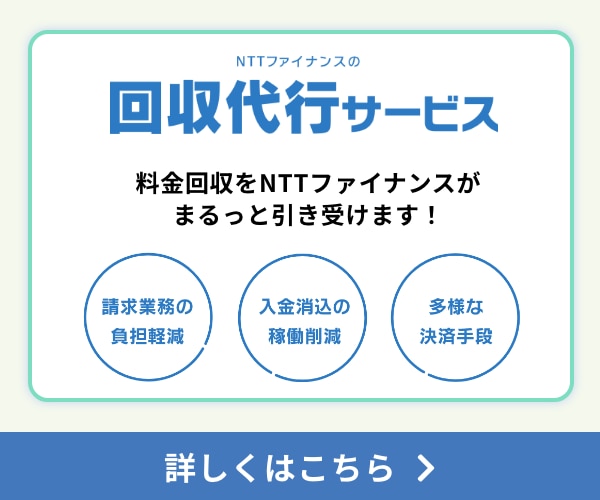請求書の発行は義務?発行すべき3つの理由や注意点・効率化の方法など総まとめ
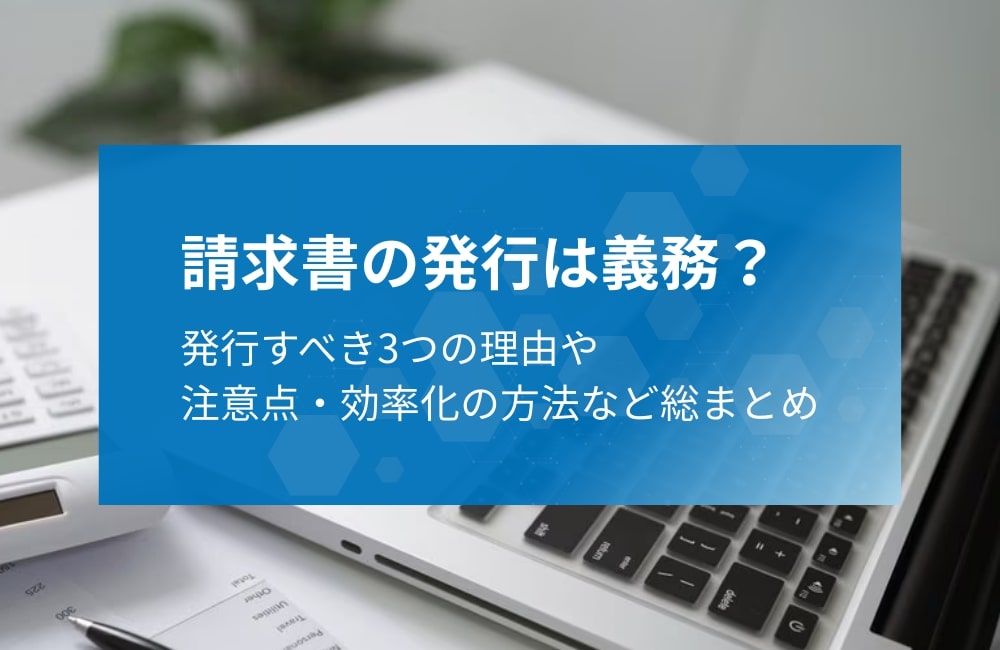
請求書は、顧客に対して商品・サービスの対価を支払うように求める役割がありますが、法律で発行が義務付けられているわけではありません。
しかし、取引が実際にあった証拠や後々のトラブルを防ぐためにも、請求書は発行するのが一般的です。
また請求書を発行する際は、インボイス制度や電子帳簿保存法との関連性を理解することが大切です。
本記事では、請求書の発行義務について触れたうえで、下記の内容を紹介します。
- 請求書を発行すべき理由
- 請求書の発行で注意すべきポイント
- 請求書の発行を効率化する方法
なおNTTファイナンスでは、「請求書の電子化を進めるメリットや注意点」をまとめた資料を無料で配布しています。資料として手元に置いておきたい方は、下記のバナーから無料ダウンロードしてお役立てください。
\電子化した請求書を発行する際の注意点も解説!/
目次[非表示]
請求書の発行は義務ではない

結論から言うと、法律上請求書の発行は義務ではなく、記載内容やフォーマットも定められていません。
とはいえ、実際に取引が行われたことの証明にもなるため、請求書は発行するのが通例となっています。
ビジネスマナーからの観点や相手との信頼関係を維持するためにも、取引が成立した場合には請求書を発行することが望ましいです。
詳しくは次の章で解説します。
請求書を発行すべき主な理由3選
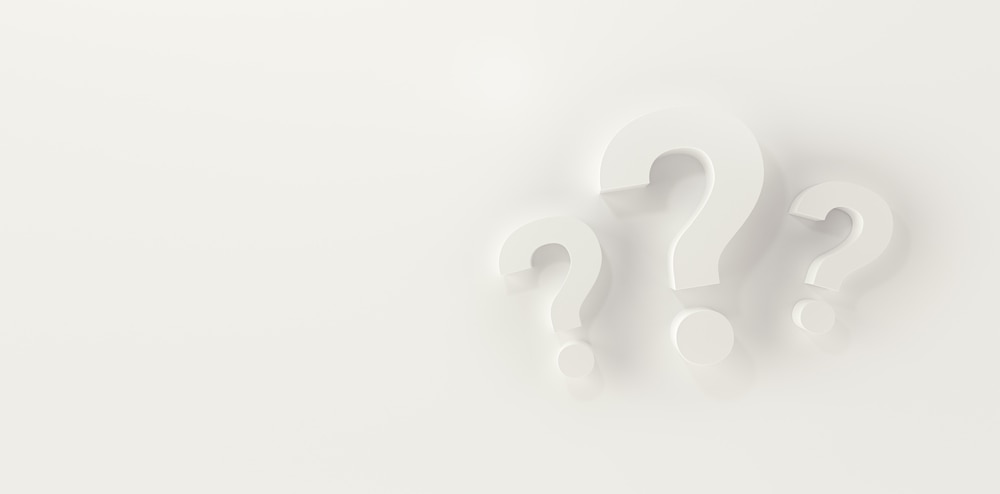
前述したように、請求書発行に義務はないものの、発行しておいた方が賢明といえます。その理由は大きく次のとおりです。
1.提供した商品・サービスの対価を求めるため
2.取引が行われたことの証明になるから
3.トラブルを未然に防ぐため
1つずつ解説します。
理由1.提供した商品・サービスの対価を求めるため
1つ目の理由は、提供した商品やサービスの対価を正当に求めるためです。
実は、口頭でも対価を請求することは可能ですが、書面に残すことで食い違いや支払忘れを防ぐことができます。
その際、金額だけではなく「サービスの内容」や「数量・単価」などの明示も忘れてはなりません。
なぜなら、正確な内容を記載することで取引の透明性が高まるほか、請求書は会計処理や正確な税務申告のための資料にもなるからです。
理由2.取引が行われたことの証明になるから
2つ目の理由は、取引が行われたことの証明になるからです。
加えて、請求書は税法上の証憑書類にもなります。証憑書類とは、取引や契約が成立したことを立証するための書類です。
請求書は、金額や支払時期などのトラブルがあった際の「裁判の証拠書類」としても提出できます。
理由3.トラブルを未然に防ぐため
3つ目の理由は、「注文した商品やサービスが違う」「約束した金額が異なる」などの認識の違いによるトラブルを未然に防ぐことができるためです。
また、取引後に何か問題が発生した場合でも、請求書によって取引の事実を証明するため、解決に役立つ証拠となり得ます。
請求書の発行で注意すべき4つのポイント

前提として、請求書の発行に明確なルールはありません。とはいえ、一般的なビジネス上のマナーに沿った内容の請求書を発行することが望ましいです。
本章では、下記4つのポイントを解説します。
請求書の不備で取引先との信頼関係を揺るがす事態に陥らないためにも、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
ポイント1.記載すべき項目を押さえる
1つ目のポイントは、請求書に記載すべき項目を押さえておくことです。
前述したように、請求書は税務上の証憑ともなる重要な役割を持っています。請求書の書式に法的なルールは存在しないとはいえ、下記の項目は記載しておきましょう。
【請求書に記載すべき項目】
|
請求書の発行日は、取引先の「締め日」に合わせるのが一般的です。そのため、あらかじめ取引先と請求締日を確認しておくことをおすすめします。
加えて、「請求番号」や「支払期限」なども、別途自社のルールに従い記載しましょう。
なお、失敗しない請求書の書き方を下記の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
ポイント2.発行方式を取引先と確認する
2つ目のポイントは、発行方式を取引先と確認しておくことです。
請求書の発行方式には、「都度方式」と「掛売り方式」があるため、契約時に取引先と取り決めておくことをおすすめします。
「都度方式」と「掛売り方式」の概要は次のとおりです。
都度方式 | 商品やサービス提供の取引の都度、請求書を発行する方式 |
掛売り方式 | 締め日に合わせて一定期間分の取引をまとめて発行する方式 |
一般的に、「都度方式」は新規での取引や個人向けで利用され、「掛売り方式」は企業相手の取引で利用されることが多いです。
ポイント3.記載内容・方法は合っているか確認する
3つ目のポイントは、記載内容・方法が合っているかを確認することです。
請求書に書く項目を決めていても、内容は取引先によって異なります。
例えば、下記のようなことを事前に確認しておくと後のトラブルを防げるのでおすすめです。
- 振り込み手数料の対応
- 消費税の端数をどうするか(切り捨か、切り上げか)など
ちなみに、消費税の小数点の端数の対応は、任意の方法で構いません。しかし、一方的に判断すると相手に悪い印象を与えかねないので、事前に取引先とすり合わせておくことが大切です。
また当たり前のことですが、記載内容に虚偽がある場合は、法律で懲役や罰金が課される恐れがあります。
例えば、インボイス制度導入にともなう下記のような行為が該当した場合などです。
【請求書発行関連の罰則の一例】
|
インボイス制度の罰則に関しては下記の記事で解説していますので、より詳しく知りたい方はご覧ください。
ポイント4.発行した請求書の保管義務について理解する
4つ目は、発行した請求書の保管義務について理解しておくことです。
前述のとおり、請求書は証憑書類にあたるため、発行した場合は控えを保管する義務があります。請求書の保管期間は次のとおりです。
- 法人:基本7年(10年のケースもある)
- 個人事業主:基本5年(7年のケースもある)
なお、メールへのPDF添付など請求書を電子的にやり取りした場合には、電子帳簿保存法で定められた要件に沿って保存しなければなりません。
当サイトでは、電子帳簿保存法の保存要件に関するお役立ち資料を無料配布しています。電子帳簿保存法で定められた要件に沿って保存したい方は、下記のバナーをクリックのうえお気軽にダウンロードしてください。
\「電子データ保存するための要件」を1冊にまとめました!/
請求書発行を効率化する3つの方法

繰り返しにはなりますが、請求書の発行は任意とはいえ、取引の際に発行するのが一般的です。毎回おこなう作業を少しでも効率化して、中核の業務に専念する時間を生み出しましょう。
本章では、請求書発行を効率化する方法を3つ紹介します。
方法1.電子化(ペーパーレス)の促進
請求書を電子化(ペーパーレス化)することにより、封筒への宛名書きや切手貼りなどの作業がカットできます。
さらに、後ほど紹介する「システム化」により定型業務を自動化すると、人的ミスの削減も期待できるほか、担当者の負担軽減も可能です。
ただし、これまで紙の請求書でやりとりしていた取引相手の場合、いきなり電子化することに抵抗を示されるおそれもあります。
そのため、請求書を電子化していない取引相手の場合は「事前に交渉する必要がある」ことを押さえておきましょう。
なお当サイトでは、請求書をペーパーレス化するメリットや進め方についてまとめた資料を無料配布しています。効率化の参考資料として、下記からお気軽にダウンロードしてご活用ください。
\ペーパーレス化の流れを完全ガイド!/
方法2.アウトソーシングの活用
アウトソーシングを活用することで、請求書発行業務の効率化が図れます。
ここでいうアウトソーシングとは、請求書の作成や発行を代行業者に外注することです。
請求金額などの「データの準備をするだけ」で請求業務を代行してもらえるため、自社で請求書の作成や発行・郵送・管理などをおこなう必要がありません。
サービスによっては、入金確認や代金回収・与信審査なども代行してくれるため、コスト削減だけではなく担当者の精神的な負担軽減も見込めます。
下記の記事では、おすすめの請求代行サービスを紹介していますので、あわせてご覧ください。
方法3.請求書発行システムの導入
請求書発行システムの導入も、業務の効率化に役立ちます。
請求書発行システムとは、請求書の発行や送付に関連する業務などを自動化・効率化できるシステムのことです。
システムの導入により、請求業務にかかる工数や人件費の削減・人的ミスの減少に貢献します。
おすすめのサービスを次の章で紹介しますので、ぜひ読み進めてみてください。
請求書発行の効率化には「回収代行サービス」が
おすすめ

NTTファイナンスが提供する「回収代行サービス」は、請求情報をご準備いただくだけで、NTTファイナンスが代わりにエンドユーザーへ請求するサービスです。
口座振替や電話料金合算では、請求ができなかったエンドユーザーに向けて自動で請求書を発行することも可能です。支払案内が確実に届くため入金漏れを防ぎやすくなり、結果として未納率の低下につながります。
【回収代行サービスの特長・導入メリット】
|
回収代行サービスはエンドユーザーごとに入金があったかを判別して消込まで自動反映できるため、入金確認にかかっていた工数を大幅に削減できる点もメリットです。
BtoB・BtoCのどちらにも対応できる「回収代行サービス」について、詳しくは下記のボタンをクリックのうえサービス資料をダウンロードしてご確認ください。
\適格請求書のフォーマットにも対応可能!/
【補足】インボイス制度で請求書の発行義務はどうなる?

大前提として、インボイス制度下では「適格請求書発行事業者」でなければ適格請求書を発行できません。
そして適格請求書発行事業者は、相手方(課税事業者)の要求に応じて適格請求書の交付が義務付けられています。
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています
インボイス制度の開始にともない、「適格請求書」には通常の請求書に記載すべき項目に加えて下記の項目の記載が必須です。
|
当サイトでは、課税・免税事業者別に押さえておきたいインボイス対応のポイントなどをまとめた資料を配布しています。下記からダウンロードして、お役立てください。
\「適格請求書」を発行する際の注意点を網羅!/
まとめ:請求書発行はシステムの導入で効率化を図ろう

本記事のまとめ
|
請求書の発行は法律上の義務はないものの、相手との信頼関係の構築や後のトラブルを回避するためにも、発行するのが賢明といえます。
毎月発生する業務だからこそ、システムの導入で効率化を図り、業務にかかる負担を減らすのがおすすめです。
なお下記の記事では、おすすめの請求書発行システムを紹介しています。失敗しない選び方も解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。