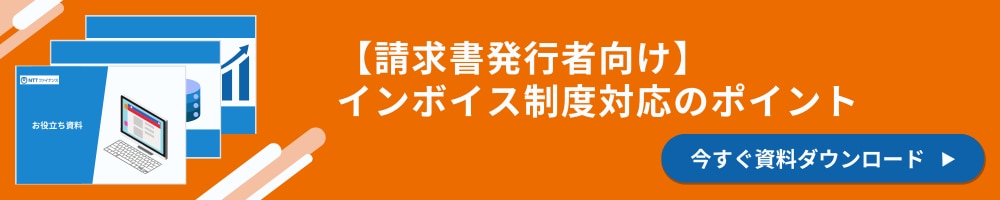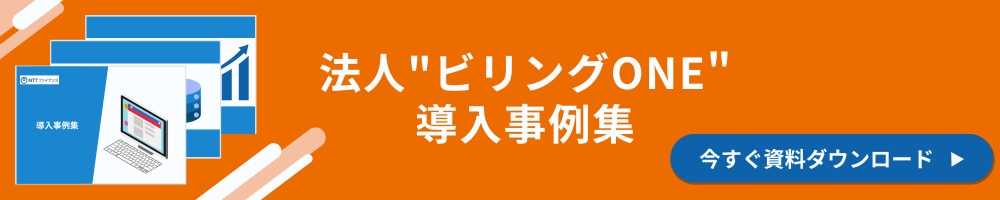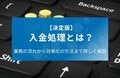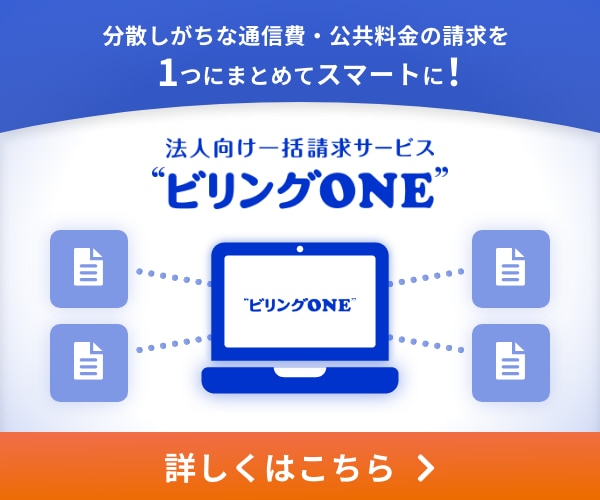請求書に明確なルールは存在しない?法律観点・記載項目・作成方法を解説
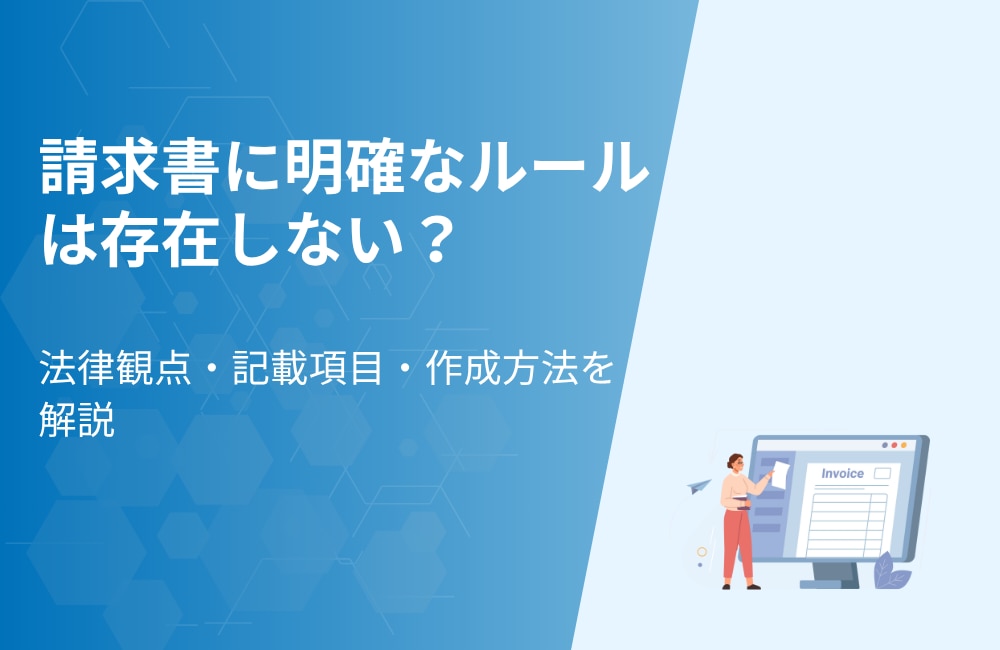
実は、請求書の作成や発行方法を直接規定するような法律は存在していません。そもそも請求書の発行自体も法律上の義務ではないのが事実です。
だからといって、発行しなくてよいかというとそれもまた違います。そこでこの記事では、下記の内容を解説します。
- 請求書を取り巻く法律上のルール
- 請求書に求められる役割
- 請求書に記載すべき項目と書き方のルール
- 請求書を作成する方法
請求書の作成だけでなく、保存期間についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
なお当サイトでは、インボイス制度に対応した請求書発行時のポイントをまとめた資料を配布しています。お手元に置いていつでも見返せる資料として、下記からお気軽にダウンロードしてみてください。
\ 保存方法と電子帳簿保存法への対応もわかる! /
目次[非表示]
【結論】請求書は単一法のルールはなく複数法で間接的に規定されている

事業運営に欠かせない請求書ですが、実は作成や発行方法を直接規定する法律は存在しません。つまり「請求書法」のような単一の法律で定められたルールはなく、発行も法律上の義務ではないのが実情です。
しかし、請求書は取引の事実を証明する重要な証憑書類であり、民法・消費税法・法人税法・所得税法・電子帳簿保存法といった複数の法律がその役割や要件を間接的に規定しています。
特に2023年10月から開始されたインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために「売り手が発行する適格請求書の保存」が必須となりました。法律で直接義務付けられていなくても、税務コンプライアンスを遵守するためには請求書の発行が実質的に欠かせません。
請求書の発行が欠かせない理由の詳細は、下記の記事をご覧ください。
請求書を取り巻く法律上の4つのルール

企業が適切に請求書を発行・保存・管理するためには、下記の4つの法律で定められたルールを把握する必要があります。
請求書は4つの法律によって、その役割や要件が間接的に規定されているため、「請求書のルール=複数の法律を横断的に理解すること」といえます。
ルール1.【民法】債権の有効期限に関するルール
請求書は債権の存在を証明する重要な証拠として位置づけられています。2020年4月施行の改正民法により、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間が実質的な有効期限です。
請求書をこの期間内に保管しておくことで、万が一取引先との間で支払いに関する紛争が発生した場合に、取引の事実と金額を法的に証明することができます。
ルール2.【消費税法】仕入税額控除を受けるための記載ルール
仕入税額控除の適用を受けるためには、法律の要件を満たした請求書の保存が必須です。2023年10月開始のインボイス制度では記載項目に厳格なルールを規定しました。
これらの要件を欠いた請求書を発行・受領した場合、控除が認められず税負担が増えるリスクがあるので注意しましょう。
なお当サイトでは、請求書として使用できるテンプレートを用途別に配布していますので、下記からご利用ください。
ルール3.【法人税法・所得税法】証憑書類の保存期間ルール
請求書は法人税法・所得税法において経費の支出を証明する証憑書類(しょうひょうしょるい)として扱われます。
このため、下記の期間は請求書を保存する義務があります。
区分 | 保存期間 |
法人 | 7年間 |
個人事業主 | 5年間 |
出典1:帳簿書類等の保存期間|国税庁
出典2:青色申告制度|国税庁
請求書の保管期間・保管方法について、下記の記事で解説していますので、さらに詳しく知りたい方は併せてご覧ください。
ルール4.【電子帳簿保存法】電子取引データの保存方法ルール
請求書を電子データで作成・授受する場合の保存方法を規定しているのが電子帳簿保存法です。
2024年1月から、電子データで受け取った請求書を紙に印刷しての保存が原則不可になりました。これにともない、電子保存を行う際には次の要件を満たす必要があります。
【電子保存の要件】
|
事業者はこれらすべての法律を横断的に理解し、適切な請求書管理を行う必要があります。
電子帳簿等保存の2つの保存要件についてさらに詳しく理解したい方は、下記の記事もご覧ください。
【ルールはなくとも】請求書に求められる3つの役割

法律で発行が義務付けられていないにもかかわらず、なぜすべての事業活動で請求書が発行されるのでしょうか。それは、請求書がビジネスを円滑に進めるための重要な役割を担っているからです。ここでは請求書に求められる下記の役割について、順に説明します。
役割1.取引の証明と代金回収の根拠
請求書の最も基本的な役割は「いつ・誰が・誰に対して・何を・いくらで提供したのか」という取引の事実を客観的に証明することです。
口頭での約束だけでは「言った・言わない」といったトラブルに発展しかねません。請求書は金額や支払い条件を明確に記載した「仕事の報酬やサービス利用で発生した料金を、指定期日までに支払ってもらうための文書」として機能し、売り手側のキャッシュフロー管理と買い手側の支払管理の双方にとっての基盤となります。
取引内容を文書化することで後日の確認や会計処理がスムーズになり、万が一の紛争時にも有力な証拠として機能します。
役割2.税務コンプライアンスを左右する重要書類
インボイス制度の導入により、請求書の役割は単なる業務上の書類から、税務コンプライアンスを左右する戦略的な書類へと変化しました。
買い手側にとって、要件を満たした適格請求書の入手は仕入税額控除を受けるための絶対条件です。不備のある請求書を受け取ると控除が否認され、直接的な金銭的損失につながります。
売り手側も「適格請求書発行事業者」として登録した場合、取引先からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が生じます。これに応じられない場合、取引関係の悪化や取引停止のリスクにつながりかねません。
役割3.取引先との信頼関係を維持する手段
迅速かつ正確な請求書の発行は、企業の誠実な業務姿勢と信頼性の証です。
逆に記載ミスや送付遅延は、相手方に余計な事務負担を強いることになります。そのうえ、自社の管理体制の甘さを露呈し、ビジネス上の信頼を損なう原因となりかねません。
インボイス制度下では「請求書の正確性」が取引先の財務に直接影響を与えるため、この傾向はさらに強まっています。長期的なビジネス関係を構築するには、適切な請求書管理が必須です。
下記の記事では、請求書関連のミスをなくして取引先との信頼関係の維持につながる「請求書発行システム」について解説しています。関心のある方はぜひご覧ください。
請求書に記載すべき項目と書き方のルール

請求書の記載項目は、取引を円滑に進めるための「ビジネスマナーとしての基本項目」と、法律(特に消費税法)で定められた「法的に必須の項目」に大別されます。
請求書に記載すべきそれぞれの項目について、説明します。
ビジネスマナーとしての8つの基本項目
法律で直接定められているわけではありませんが、取引の明確化とトラブル防止のために記載することが強く推奨される項目があります。下記の8つの基本項目を押さえておきましょう。
項目 | 記載内容 |
1.題目 | 書類の最上部に「請求書」と大きく記載 |
2.請求先 | 取引先の正式名称(会社名・部署名・担当者名)。法人は「御中」、個人は「様」 |
3.発行者 | 自社の名称・住所・電話番号などの連絡先 |
4.発行日 | 請求書を作成した日ではなく、取引先と取り決めた「締日」を記載 |
5.請求書番号 | 請求書を一枚ずつ識別するためのユニークな番号 |
6.請求金額(合計) | 消費税などを含めた最終的な支払総額を目立つように明記 |
7.振込先 | 銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義 |
8.支払期限 | 事前に取り決めた支払期限日を明記 |
これらの基本項目は、取引を円滑に進めるための土台となります。特に発行日や支払期限などは、事前に取引先と確認しておくことがトラブル防止の鍵です。
請求書を失敗せずに作りたい方は、下記の記事をご覧ください。
法的に必須の項目:適格請求書(インボイス)の6つの要件
2023年10月1日以降、買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手が発行する適格請求書の保存が必要になりました。適格請求書には下記の6つの必須項目があります。
項目 | 記載内容 |
1.発行事業者の氏名または名称および登録番号 | 税務署から通知される「T」で始まる13桁の登録番号を記載 |
2.取引年月日 | 商品やサービスの提供が完了した日付 (請求書の発行日とは異なる場合があるため注意) |
3.取引内容 | 提供した商品やサービスの内容を具体的に記載。軽減税率(8%)の対象品目は「※」などで明示 |
4.税率ごとの合計額および適用税率 | 標準税率(10%)と軽減税率(8%)をそれぞれ分け、税率ごとの合計金額と適用税率の両方を明記 |
5.税率ごとの消費税額 | 税率ごとの合計金額に対して消費税額を計算。端数処理は税率ごとに1回ずつのみ |
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 請求書を受け取る取引先の正式名称を正確に記載 |
これらの要件を満たさない請求書では、買い手側は仕入税額控除を受けられず、税負担が直接的に増加してしまいます。下記の記事では、インボイス制度に対応した請求書の書き方を解説していますので、参考にご覧ください。
請求書を作成する3つの方法
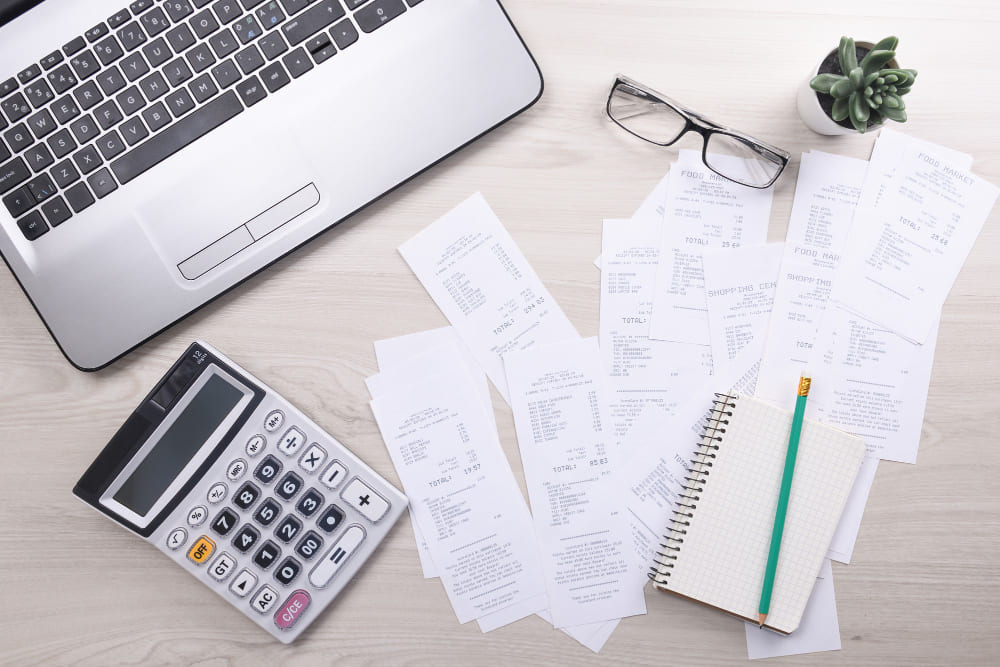
請求書を作成する方法は、主に3つあります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の事業規模や業務フローに合った方法を選択することが重要です。
方法1.紙で作成する
デジタルツールを一切使わないため、PC操作が苦手な場合でも作成可能です。取引件数が極端に少ない個人間の取引などでは、選択肢となり得ます。
ただし作成・印刷・封入・郵送といった一連の作業に多大な時間とコスト(紙代・印刷代・郵送費)がかかります。さらに物理的な保管スペースが必要で、書類の紛失や劣化のリスクもともないます。
正直なところ、現代のビジネス環境、特にペーパーレス化やリモートワークの潮流とは適合しにくい方法といえるでしょう。
方法2.ExcelやGoogleスプレッドシートを活用する
多くのPCに標準でインストールされているうえにテンプレートも豊富に存在し、手軽に利用できるのが魅力です。ただし、手作業による入力ミスや計算間違いが起こりやすい点が最大のリスクとなります。
特にインボイス制度で求められる税率ごとの計算や端数処理は複雑であり、誤りが発生すると請求書が無効になるおそれがあります。取引件数が少ない事業者や、まずは低コストで始めたい場合に適した方法です。
方法3.クラウドサービス(請求書発行システム)を利用する
インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正に自動で対応してくれるため、コンプライアンスリスク(法令を破るおそれ)を大幅に低減できます。請求書の作成から送付、入金管理までを自動化できて、ヒューマンエラーの削減と業務効率の大幅な向上につながります。
加えてクラウドサービスのため、テレワーク環境でも場所を選ばずに請求業務を行える点も大きな利点です。ただし、月額利用料などのランニングコストが発生する点には考慮が必要です。
請求業務を効率よく進めたいなら「法人"ビリングONE"」もおすすめ
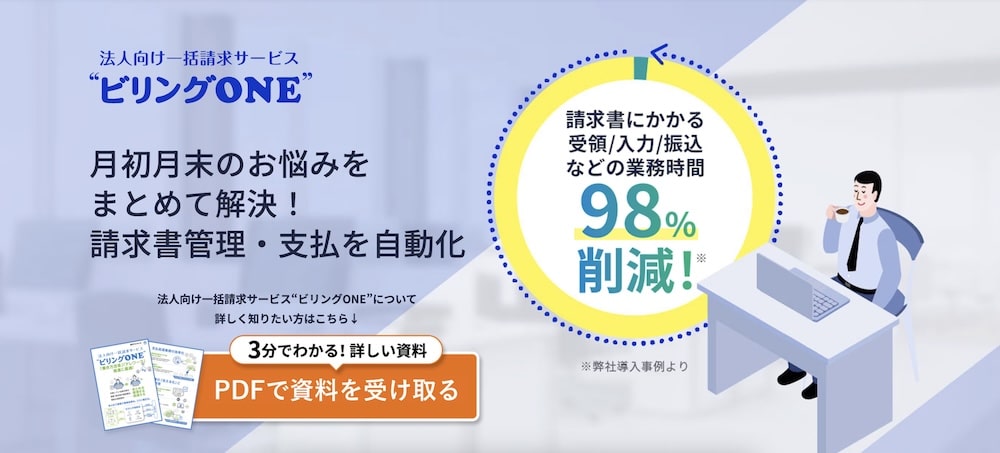
請求書は「発行する側」だけでなく、自社が「支払う側」としても日々やり取りする重要な書類です。取引先や拠点ごとに支払い期限や請求書の形式が異なると、支払い漏れや確認作業の手間が増え、経理部門の負担にもつながります。
そこで請求書の業務をルールに則って効率化するなら、インボイス制度にも対応しているNTTファイナンスの「法人"ビリングONE"」がおすすめです。
「法人"ビリングONE"」は、支払期限が異なる請求書(通信費・公共料金・その他)をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 要問い合わせ |
対象の請求書 | 通信費・公共料金・その他 |
複数の拠点ごとにバラバラに届く請求書や、支払期限が異なる請求書を1枚の電子請求書(紙請求も可)にまとめることで、支払い処理を1回にできます。
従来の請求書の開封・支払い・保管の負担を軽減できるため、複数枚届く請求書や何通も届くメールの処理にかかっていた経理業務の大幅な効率化が可能です。
クラウド上で一元的な管理ができる「法人"ビリングONE"」の詳細は、下記からサービス資料をダウンロードのうえご確認ください。
\請求書の受領から管理・支払いまで完全自動化!/
具体的な導入後の声を確認してみたい方は、下記の記事をご覧ください。
請求書に明確なルールは存在しなくても法律に準拠した内容で作成しよう

【本記事のまとめ】
|
請求書の作成ルールは、単一の法律がなくとも複数法で間接的に規定されています。間違った理解で作成してしまうと取引先に迷惑がかかり、信用も信頼も失墜しかねません。
本記事を参考に「正しい請求書」を作成して、スムーズな処理を実行していきましょう。
なお、請求書の業務をルールに則って効率化するなら、インボイス制度にも対応しているNTTファイナンスの「法人"ビリングONE"」がおすすめです。
「法人"ビリングONE"」は、支払期限が異なる請求書(通信費・公共料金・その他)をNTTファイナンスが一度立て替え、その後にお客さまへ一括請求するサービスです。
請求書の支払処理の負担を軽減できる「法人"ビリングONE"」の導入事例については、下記のバナーをクリックのうえ資料ダウンロードしてご確認ください。
\自社での導入効果をイメージできる!/